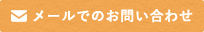【弁護士倫理】弁護士は、虚偽のアリバイを証言すると予想される証人を、証人尋問申請すべきか
2023年04月22日読書メモ
弁護士倫理の議論で「フリードマンの3つの難問」、すなわち、①偽証することが分かっている被告人(証人)を証言台に立たせてもよいか、②真実だと分かっている証言の信用性を減殺するために反対尋問をしてもよいか、③被告人に教えると偽証を誘導するおそれがあるような助言してもよいか、というものがあります。この記事は、①について、私の考えを述べたものです。
まず、弁護士職務基本規程5条は次の通り定めています。
第5条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
このように、弁護士には真実を尊重する義務と、依頼者への誠実義務が課せられています。もっとも、ここでいう真実義務とは消極的真実義務といわれます。
弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説弁護士職務基本規程(第3版)』(日弁連,2017年12月)11頁
【本条の規定する「真実を尊重し」ということは、刑事事件において、弁護人に実体的真実(客観的真実、事件の真相)の発見に積極的に協力する義務(以下「積極的真実義務」という)を課すことを定めるものではない。刑事事件において被疑者、被告人の有罪を立証する義務はあくまでも訴追者である検察官に課されているのであり、弁護人にはそのような積極的真実義務は課されていない。被疑者・被告人には憲法上黙秘権が保障されており(憲38条)、これらの者に積極的真実義務がないことは明らかである。したがって、被疑者・被告人に対して誠実義務を負う弁護人にも積極的真実義務がないことも明らかである。職務基本規程82条1項は、 「第5条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない」と規定し、 この旨を注意的に明らかにしている。
しかし、弁護人といえども裁判所・検察官による実体的真実の発見を積極的に妨害し、あるいは積極的に真実を歪める行為をすることは許されない(以下「消極的真実義務」という)。職務基本規程75条も、 「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」と規定し、 この消極的真実義務があることを明らかにしている。
以上のように見ると、弁護人にとって、刑事訴訟法1条に定める「事案の真相を明らかにする」ということは、 もっぱら被疑者・被告人の免責あるいは刑の軽減の方向に限られ、検察官の有罪立証の義務が尽くされていないことを指摘し、 また、被告人に有利な事実の存在を明らかにすることを意味するといえる。弁護人は、いかなる状況のもとにおいても、検察官の補助者となるものではなく、検察官と弁護人のこうした役割の分担とその適切な共働(ないし対立・拮抗)関係(対審構造)こそが、社会正義に適う裁判の基礎となるものである(注釈倫理39頁)。】
しかし、消極的真実義務といえども、時に誠実義務と対立します。その典型例が、虚偽のアリバイを証言する証人を申請すべきか、ということです。これは、古典的な問題ですが、いまなお議論の一致がなく、職務基本規程の解説書でも結論は述べられていません。弁護士職務基本規定75条の問題もあります。
第75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説弁護士職務基本規程(第3版)』(日弁連,2017年12月)13頁
【①有罪事件の無罪主張
被告人が法廷で無罪を主張しながら接見中に弁護人に対して有罪を告白したような場合に、弁護人が有罪主張をすることは誠実義務に反し、無罪主張をすることは真実義務に反するように見えるため、弁護人としてはどのようにしたらよいかが問題となる。
弁護人が告白内容を無断で開示することは守秘義務(法23条、職基23条)に反することが明らかであり、 もとより許されないが、被告人が有罪を告白しながらもあくまで無罪主張を維持したいと述べる場合には、事件の見通しを十分に説明し、かえって悪い結果を導くことがあり得ることを説明すべきである。それでも翻意しない場合には、弁護人としては被告人が犯人であると知っていても無罪主張をせざるを得ない。この場合には、弁護士倫理上の難問(フリードマンの3つの難問)、すなわち、①偽証することが分かっている被告人(証人)を証言台に立たせてもよいか、②真実だと分かっている証言の信用性を減殺するために反対尋問をしてもよいか、③被告人に教えると偽証を誘導するおそれがあるような助言してもよいか(英米法では被告人も宣誓すれば証人になれるのでこのような問題提起となる)という問題に直面することになる。具体的な弁護の方法次第では誠実義務に反することになるケースがあり、逆に消極的真実義務に反するケースもある。】
検討のため、いくつか文献を調査しました。
まず、職務基本規程の制定前の文献ですが、そもそも、弁護人の真実義務を否定する考え方がありえます。その場合でも、上記フリードマンの難問に対する回答は異なるのですが、偽証するとわかっていても通常通り尋問するという考え方もあるようです。
日本弁護士連合会『平成8年度研修版現代法律実務の諸問題』(第一法規,1997年10月)
村岡啓一「刑事弁護人の誠実義務と真実義務」
722頁
【私自身は、真実義務を否定する考え方に立っております。高野隆弁護士も同じであります。それから、当番弁護士協議会で法務省の見解に対し反論をしている日弁連の委員もこの真実義務を否定する立場に立っております。
それはなぜかというと、たまたまみんなの思考が一致したからということではないのです。それには理由がありまして、日本国憲法が刑事弁護人をどのように位置づけているのかを探求し、被疑者・被告人の立場が刑事訴訟の中でどのように位置づけられているのかを考察していくと、弁護人の真実義務を否定するよりほかはないという結論にたどりつくからです。つまり、理論的に一致しているからなのです。そのことを次にご説明いたします。】
733頁
【これに対しては次のようにフリードマンは考えていますし、私たちも正しいと思っています。それは先ずは、翻意を促すべきである、つまり偽証する証人を証言台に立たせるべきではない、あるいは被告人がうそを言うと知っていて、そのとおり言わせるべきではない。そんなことを言っても裁判所はだまされないよということを説明して翻意を促すべきである。それは、法律専門家として依頼者に対する誠実義務の履行です。しかし、その説得にもかかわらずあくまでも本人が偽証に固執するのであれば、弁護人は普通の場合と同様のやり方で尋問し、その得られた証言に基づいて弁護するしかない。これは私を含め、弁護人の真実義務を否定する考え方を支持する者の共通した答えです。
二間は、真実だとわかっている適性証人の証言の信用性を暴くために反対尋問をするべきかというものでした。
これも弁護活動としては当然やるべきであるという結論になります.訴訟的な真実というのは、先ほども言いましたように、攻撃・防御を尽くした中から浮かび上がってくるものをもって真実とみなすということです。そうであるならば、その信用性を弾劾するべきは、やはり弁護人として依頼者のために誠実に行うべき当然の弁護活動であると考えられます。
三間目は、被告人に教えると偽証を誘発するおそれがある場合、つまりこの情報を与えるとそれはいい提案だと受け止めて、その方向に引きずられてうそを言う可能性がある場合、それを知っていて助言をするべきかというものでした。
これはかなり難しい問いなのですが、いろいろ場面としては考えられます.例えば、組織犯罪などの場合にどのレベルで手打ちにするか、選挙違反のときにどのレベルの責任でおさめるか等々の相談を受けた場合、弁護士としてどうかかわるか。これは微妙な回答なのですが、ある事実に対しての法的効果を説明することは許されてよいというものです。しかし、明らかに自分の助言が原因となって依頼者が犯罪を犯すような場合とか、不正行為や偽証を誘発する場合、あるいは当事者主義のルールに反するような形で依頼者を巻き込むことは許されません.何かわかったようでわからない回答なのですが、簡単に言うと、ある事実に対しての法的効果だけ説明して、後は相手方に決断をさせなさいということです。弁護士の方からこうやれ、ああやれと指導をすることは弁護士倫理に反するということです。果たして、皆様方はこの回答に納得されたでしょうか?時間が来ましたので、これで私の講演を終わらせていただきます】
一方で、否定的な考え方もあります。
季刊刑事弁護22号(2000年夏号)18頁
後藤昭「刑事弁護人の役割と存在意義」
【このような前提の一致のために、被告人が無罪判決を望んでいる場合のように、依頼者の希望とその客観的利益とが一致する限りは、村岡的立場と上田的立場の違いが表面に出るのは、微妙な限界事例に限られる・典型的には、偽証するとわかっているアリバイ証人を提出し、あるいは尋問するような場合である・上田はこれを許されないとし、村岡は、むしろするべきであるという・私自身は、この種の場面での基準として、「弁護人が助けようとする行為が、依頼者本人にとって適法になし得る行為か否か」という判定方法を考えている】
現代刑事法-その理論と実務- 2004年2月号(58号)34頁
捜査における弁護人の役割
桃山学院大学法学部教授小早川義則
【ところで、この誠実義務純化論の提唱者である村岡啓一教授は、有名なフリードマンの難問「偽証することが分かっている被告人を証人台に立たせるべきか」に対し、1983年アメリカ法曹協会「弁護士業務模範規則」は、1被告人自身に物語風の証言をさせる、2被告人に対し翻意を促すべきだが、あくまでも偽証に固執する場合には、普通の場合と同じやり方で被告人を尋問し、その証言に基づいて弁護する、3弁護人としての偽証の事実を明らかにしなければならない、この3つの解答を併記しているとした上で、提唱者は2の解答を支持する。そしてフリードマンの問いかけを「証人」に一般化して、「弁護側証人の偽証を黙過することは許されるか」といった形で問題化すべきであると主張するのである(10。いずれにせよ、フリードマンの難問をめぐる「アメリカでの議論状況を前提」にしている(15)ことは明らかである。
アメリカでは「未だに議論の決議をみていない」とされるが、合衆国最高裁は1986年のホワイトサイド判決06)でこの問題に関連する興味深い判断を示しているので紹介しておく。正当防衛に関する偽証の意思を示した被告人に対し、国選弁護人が偽証をすれば裁判所にその旨報告すると伝え、さらに偽証に固執するのであれば裁判所に弁護人の辞任を求める等と伝えて偽証を阻止したところ、有罪判決後に被告人が憲法上の効果的な弁護人の援助を受ける権利を否定されたことを理由に原判決破棄を求めた事案につき、全員一致で、ミランダに弾劾例外を肯定した1971年のハリス判決(Harrisv.NewYork,401U.S, 222)等を引用しつつ、憲法は偽証を保障するものではないとして、本件弁護人の行動は合理的な弁護活動の範囲内である旨判示した。「要するに、裁判所の構成員として(asofficerofthecourt)、かつ司法制度の重要な構成要素として真相解明に貢献する(dedicated)弁護人の倫理責任は、依頼者が証人や陪審員への賄賂や脅迫の意図を告知したか、それとも偽証の意図を告知したかにかかわらず、本質的に同一である」と判示したのである。
もっとも、同判決は合衆国憲法第6修正の弁護人依頼権とのかかわりで被告人の偽証阻止が問題とされた事案で、「アメリカでは被告人の証人適格が認められているために、依頼者の偽証を助けることの適否が深刻な問題とされる」のであり、わが国の議論に「そのまま」当てはまるものではない(17)。しかし、アメリカでも被告人は証人台に立った以上、その立場は一般の証人と同一であり、前述のようにわが国の誠実義務純化論者も、そのことを承知した上で、弁護側証人の偽証一般とのかかわりを問題にしているのであるから、わが国の議論に有益な素材たりうることは否定できない。とりわけ「裁判所の構成員」として「真相解明に貢献する弁護人の倫理責任」を明示した点は、誠実義務純化論の是非についてはもちろん、弁護人の真実義務ともかかわるだけに、わが国の議論の深化に役立つように思われる。もっとも、フリードマンの難問については不案内であるので、その詳細な検討は後日の課題としたい。】
武井康年・森下弘編著『ハンドブック刑事弁護』(現代人文社,2005年4月)288頁
【〔設問56〕虚偽のアリバイ証言
Xは、殺人事件の被告人Aの弁護人である。
①Aから「友人のBに頼めば、私のアリバイを証言してくれます。そのことをBに頼んでほしい」と依頼され、Bに面談したところ、 「Aにアリバイはないが、Aを助けたいのでアリバイを証言してあげる」 と言われた。Xは、Bを証人として証拠調べ請求をしてもよいか。】
291頁
【2小間①について
前記の視点や問題点を前提に〔小間①〕を考えると、Bは証人として証言をすることが前提となっているので、Bの偽証に対する教唆犯が成立するのではないかが問題となる。
XがBに対して、 「Aが嘘のアリバイを証言するように要請している」と伝言すれば、偽証教唆罪の成立は免れないであろう。また、Aの要請を「暗に」伝えたとしても、教唆をしたか否かの事実認定の問題は残る。 「暗に」であればよいわけではない。
XがBに対して、Aの意向を伝えたのではなく、たんに「アリバイを証明できるのか否か」と尋ねたのに対して、 Bが「Aにアリバイはないが、私はAを助けたいので、 アリバイを証言してあげる」と言った場合には、Xには偽証教唆の実行行為はないと言える。
しかし、偽証することが明確になったうえでXがBを証人とする証拠調べ請求を行うことについては、結局、前述のフリードマンによる検討と同様に、三説が成り立ちうることとなるが、積極的にBを証人とする証拠調べ請求をすることが許されるとまでは言えないのではなかろうか。
Bが虚偽のアリバイ証言を行い、後にこの証言が虚偽であることが判明した場合、Aは窮地に立たされる。Xは、Aに対し、その危険性を十分に説明し、Bを証人とする証拠調べ請求は行わないようにすべきであろう。】
岡慎一・神山啓史『刑事弁護の基礎知識 第2版』(有斐閣,2018年12月)
25頁
【(1) 虚偽証拠等提出禁止規範と刑事弁護
弁談士には, 「虚偽であることを知っている証拠」の提出禁止(弁護上職務基本規程75条参照)等の規範が存在する。この規範は.裁判所の判断資料として提出される証拠等は虚偽のものであってはならないとするルールであり,実体としての真実に対する義務ではないから, 「真実義務」と呼ぶのは適切でない。
これに対し,弁護活動の限界は「刑法などの一般的禁止規範及び刑事脈訟法などが定める訴訟法上のルール」であり, 「禁止される限界は, 明確な犯罪に限定されるべき」(村岡啓一「被疑者・被告人と弁護人の関係①」季刊刑事弁護22号〔2000年〕26頁, 27頁) とする見解がある。この見解は,被告人の自己防御権保障が弁護人の役割であることから, 弁誰人の規範は被告人自身
の規範と同じでなければならないとするものと考えられる。しかし, 虚偽証拠提出禁止等の規範は,放判手続の公正ないし尊厳を批なわないために法律家に要求される普遍的規範である以上(ABA法律家職務棋範規範173頁の同規則3.3についての注釈参照) , 刑事手続でも妥当するといわなければならない。法はこうした職務規範が弁護士に存在することを前提に,弁護士資格を有する者からの弁護人選任を原則としたものと解されるから被告人自身は行えるが弁護人はできない行為があることは予定されていることになる。
そして. 弁護人に法律専門家としての規範があることが, 弁渡人の立証活動に対する信噸の基盤になり, そのことが弁護人の援助を受ける権利の実質的保障に資するということができる。】
27頁
【(イ) 証人尋問
虚偽の事実を供述しようとする証人について証拠調べを詰求し、 質問することは、偽証教唆や幇助に該当しないとされる場合でも、虚偽証拠等の提出禁止規範に違反するから、弁護人が行うことは許されない。
また, こうした証人を被告人が請求することについても、 偽証教唆に問われるおそれがあるから行うべきでないと助言する必要がある(被告人が, 自己の刑事事件について他人に偽祉を教唆した場合について、判例・通説は偽証教唆罪の成立を肯定している)。
(ウ)被告人の供述
被告人が公判で虚偽の事実(例えば, 虚偽のアリバイ) を主張しようとする場合, 弁護人が被告人質問を申し出ること(そして被告人に質問すること)は許されるかが問題となる。
この点については,現行法の被告人質問手続は被告人が主張を述べる機会としても位置づけられるから, 同手続で被告人が主張したいとするときには,虚偽供述がなされることを弁護人が知った場合でも, 被告人質問を申し出て質問を行うことはできるとする考え方(許容説) もある。
しかし、被告人の公判供述は証拠となるのだから、 虚偽の供述がなされることを知った場合に被告人質問を申し出たり,被告人に質問することは,虚偽証拠等提出に当たり許されないと解すべきである。この場合、被告人が被告人質問手統で主張を行おうとするときは、自ら裁判所に発言の機会を求めることができる(刑訴311条2項)。被告人質問は、通常は,弁護人が申し出る運用が行われているため,被告人が申し出ると、弁護人が被告人供述が虚偽であることを知っているのではないかと受け止められるおそれはあるが, 「虚偽の供述をすると弁護人が知った」という例外的な場合にこのような受け止めがなされるうるとしても, そのことを回避するために虚偽証拠提出が許される場合を認めるのは, 虚偽証拠提出禁止規範が弁護人人の立証活動に対する信頼を確保する意義を有するものであることにてらしても, 妥当とは思われない(岡=神山2013・112頁では許容説を支持したが.上記のとおりに改める)。】
私の意見としては、少なくとも、「嘘をつくことには一切協力できない」といって拒絶することは、弁護士倫理上許容される(最善弁護義務違反にはならない)とされるべきだと思っています。本人が否認する以上、証拠不十分という無罪弁論はすべきですが(誠実義務の履行で、真実義務違反にもならない)、積極的に嘘の証拠を提出することには協力する義務はない、と。このように、「拒絶」することを許容することは、弁護士の身を守ることにも繋がると思っています。そのため、弁護人が、虚偽と認識したアリバイ証人を申請する義務がある、という考え方には与しません。
その上で、嘘と告知された上で協力する弁護活動がどこまで許されるか、だと思います。
まず、真実義務がないとして無制限に協力ができる、というのであれば、それは本来許されない証拠偽造や犯人隠避を弁護人に限って認めることにつながるのではないかと疑問があります。弁護人が、接見交通権を初めとした特権を与えられているのは、高い倫理と専門性があるからであって、被疑者・被告人の嘘を手助けするためではないと考えています。そうすると、被告人が被告人質問で「嘘」を述べることを予期しながら尋問することまでは自己決定権の尊重であり、弁護人が嘘をつかせるわけではないので許容されるものの、被疑者・被告人から「嘘」と告知された上で、虚偽のアリバイ証人を申請する行為については、許容されない、とすべきではないかと思っています。
要するに、「嘘」と言われた場合、弁護人は、黙秘権の行使はもちろん勧められるし、被疑者・被告人の嘘を止める義務はないけども、その嘘に積極的な協力はできない、ということです。上掲の文献でいえば、許容説にあたると思います。
私の考え方について異論はあるでしょうが、私自身はそういった見解の下で弁護活動をしています。