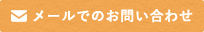執行猶予期間経過後の再犯事件について、執行猶予判決をとるための弁護活動
2024年01月19日違法薬物問題
執行猶予期間中の再犯については、法律上、原則として実刑になります。このことは広く知られているところですが、執行猶予期間が経過した後の再犯についてはどうでしょうか?実は、これも実刑になることが多いです。とりわけ、同種犯罪の場合は、反省がないということで実刑になる可能性は高まります。ただ、法律上は執行猶予を付すことも可能ですので、犯罪の内容、弁護活動と、裁判官の考え方次第では執行猶予が付されることもあります。
第1 原則として実刑になること
基本的に、執行猶予期間満了後の再犯については、実刑という判断がなされると考えるべきです。例えば、裁判官が量刑判断にあたって必ず参照する文献、植野聡「刑種の選択と執行猶予に関する諸問題」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第4巻 刑の選択・量刑手続』(判例タイムズ社,2011年12月)62~63頁には次のような記載があります。
【執行猶予満了後の再犯
後記7のとおり,執行猶予期間は, その一つの側面として,被告人が執行猶予の取消しという心理的強制を加えなくても更生の道を歩むことができるようになるまでの,一応の見込みの期間という意味合いを持つ。しかし,これはあくまで前刑判決時の一応の見込みにすぎず,肝心なのは,単にその期間が経過したかどうかではなく, その被告人が真実更生の道を歩んでいるかどうかである。執行猶予期間が経過したことは,前刑の執行猶予を取り消される可能性がなくなったことを意味するにすぎず,被告人が更生したことを意味するわけでもなければ。ましてや,法律上,被告人を初犯の場合と対等に取り扱うべきことを意味するものでもない。前刑の際の手続を通じて,自分の規範意識の不足や行動性向上の問題点等を認識し,社会内で更生を果たす機会を与えられたのに,再び罪を犯した以上, それは,少なくとも, その時期が執行猶予期間満了後短期間である場合は, 更生を果たす機会を自ら放棄したことにおいて,執行猶予期間中の再犯の場合とさほど本質的な開きはない113)。
実刑と執行猶予との選択を,初犯の場合に準じた基準で行うことが許されるか否かは、結局被告人がいったんはほぼ完全に更生していたと評価すべきか,犯罪性向が解消されず、更生を果たさないまま再犯に至ったと評価できるかに係っているであろうが,執行猶予期間満了後(あるいは執行猶予に係る判決の宣告後)特定の年数をもって, この両者を分ける目安とするのは難しい。ただ, ごく抽象的にいえば, 執行猶予期間満了から11 2年程度では’仮に, その間に犯罪が発覚しなかったのみならず,実際に犯罪に関与した事実が全くなかったとしても’ それだけで更生を遂げていたといえるかどうか疑問であるし,将来の予測の問題としても, その程度の期間で再犯に陥ったという負の実績がある以上、再犯可能性が低いと予測することはなかなか困難である。したがって, その程度の場合に執行猶予を付する方向で考えることは難しい。ただ,再犯までの期間が同じであっても,前の犯罪と同種事犯であるかどうかのほか, その間,それなりに安定して健全な社会生活を送っていたか,職業が安定せず,前件の一因となった不良な人的交友関係も解消されていないなど。更生意欲に疑問が残るような生活態度であったか,再犯までの間犯罪と完全に絶縁していたか否かなどにより,最終的な評価は当然異なり得る114)。そして,一応更生して生活していたといえるかどうかの限界線上にあるような場合には,保護観察付きの執行猶予とする選択肢も考慮に値するであろう。
具体的にどの程度の期間を経過すれば執行猶予を付する方向で考えられるかについては,本研究会での意見にも, ある程度の幅が見られた。】
田村政喜「33 執行猶予の判断基準」池田修・杉田宗久編『新実例刑法[総論]』(青林書院,2014年12月)450頁も同旨です。
【(3)執行猶予期間経過後の再犯の場合
執行猶予期間経過後の再犯の場合,執行猶予期間の経過により刑の言渡しが効力を失うから,刑法25条1項1号による初度目の執行猶予が可能である。しかし,執行猶予期間が経過したことは,被告人が更生したことを意味するわけではない。法律上,被告人を初犯の場合と対等に取り扱うことを意味するものでもない。前刑の際の手続を通じて,社会内で更生を果たす機会を与えられたのに再び罪を犯した以上,少なくとも, その時期が執行猶予期間満了後短期間である場合は,更生を果たす機会を自ら放棄したことにおいて,執行猶予期間中の再犯の場合とさほど本質的な開きはない。実刑と執行猶予との選択を初犯の場合に準じた基準で行うことが許されるか否かは,被告人がいったんはほぼ完全に更生していたと評価できるか,犯罪性向が解消されず更生を果たさないまま再犯に至ったと評価できるかに係っている(植野・前掲62頁)。】
そのため、執行猶予期間直後の犯行(特に執行猶予期間中に、立件はされていなくても既に再犯をしている場合)については、実刑が避けられないとみた方が良いことが多いです。ただ、この場合でも一部執行猶予付の判決を求めることで、服役する期間を短くすることができる場合はあります。
第2 例外的に執行猶予判決となることもあること
もっとも、執行猶予期間経過後の再犯が、必ずしも実刑しかないということではないです。執行猶予期間経過後は、法律上は無条件に執行猶予にすることも可能なのですから、再度の執行猶予を検討するような良い情状がある場合には、執行猶予にすることも少ないないとされてきました(虎井寧夫『令状審査・事実認定・量刑』(日本評論社,2013年9月)299頁以下に万引き事案について再度の執行猶予を付した事例が紹介されています)。
【第9問 執行猶予期間経過直後に犯した事件の量刑はどう考えたらよいでしょうか。
まず、執行猶予になった事件と同種の場合と異種の場合では少し異なるでしょう。執行猶予期間が経過したといっても、同種事件の再犯の場合は犯情がよくないので、執行猶予期間が経過しているというだけで軽々に再び執行猶予にはしがたく、執行猶予期間の末期に行った場合とさほど異ならず、実刑判決は十分あると思われます。特に、執行猶予期間中から、同種犯行が始まっていたことが窺われると、実刑の可能性が強いといえるでしょう。
これに対して、新事件が前の事件と全く性質の違う事件であれば、新事件についてさらに執行猶予もあると思います。
もとより、執行猶予期間が経過して問もない場合は、無条件に執行猶予にすることも可能なのですから、猶予期間中であっても再度の執行猶予を検討するようなよい情状があるケースでは執行猶予にすることも少なくないでしょう。
前の執行猶予期間が、例えば5年間で長すぎると評価される場合などは、その点が執行猶予にするための一要素となることもあるかもしれません。】
また、原田國雄「量刑における回復・治療プログラム参加の意義-裁判官としての経験から-」(原田國男『裁判員裁判と量刑法』(成文堂,2011年11月)199頁~)201頁には、覚せい剤依存症の被告人につき再度の執行猶予判決を下した経験が語られています(原田國男『量刑判断の実際〔第3版〕』(立花書房,2008年11月)215頁)。
特に、前刑から一定の期間(10年間以上)が経過している場合には執行猶予判決となることは十分にあり得ます。私が担当した覚せい剤自己使用事件(13年前に同種前科あり)でも、取調べで当初否認していましたが、自白に転じ、入手先を明かした上で依存症離脱のための更生支援をすることで、無事に執行猶予判決を得たことがあります。
さらに、近時、万引き事案については、責任能力を肯定しつつも、再犯防止の観点から、再度の執行猶予を付す事例が増加しています(城下祐二「クレプトマニア(窃盗症)・摂食障害と刑事責任」刑事法ジャーナル72号(2022年5月号)19頁~、竹川俊也「万引き」と責任非難・量刑」山口厚ほか編『高橋則夫先生古稀祝賀論文集[下巻]』(成文堂,2022年3月)57頁~)。こういった視点からの弁護活動も考えられるでしょう。そして、令和4年6月13日、通常国会において「刑法等の一部を改正する法律」が成立したことも重要です。同改正では、再度の執行猶予の範囲が拡大されました。これは、改善更生・再犯防止を図る観点からは、必ず実刑とするのではなく、社会内処遇を続けさせる方が適当な場合もあるとの観点からなされたものです。この改正がなされたことは、法律の施行前であっても十分考慮すべき要素です。従前のように、執行猶予期間満了直後の再犯は原則実刑といった硬直的判断をせず、再犯防止のためには何が適切かという観点から判断がなされるべきと考えます(改正の趣旨につき、栗木傑・中野浩一「刑法等の一部を改正する法律の概要」法律のひろば75巻9号(2022年9月号)51頁~、橋爪隆「自由刑に関する法改正」法学教室2022年12月号(507号)44頁~)。
基本的な弁護活動としては、下記記事の対応と同じになりますが、執行猶予期間経過後の犯行であるということを強く意識して、何故、もう一度執行猶予付判決をするべきなのか論じなければなりません。
第3 近時の取扱例
例えば、私が昨年取り扱った無免許運転の事例は、執行猶予期間が満了した約4年後に無免許運転をしたというものでしたが、無事に執行猶予判決を得られました。同判決においては「交通規範意識の低さ、常習性は顕著であり、本件について、実刑判決をもって臨むことも十分に考えられる。」と述べられつつも、種々の事情を考慮した上で「その刑の執行を猶予した上で、その猶予の期間中保護観察に付することとして、主文のとおり判決することとした。」として5年間の執行猶予付判決(保護観察付)を得ることができました。
※関連記事