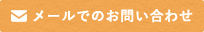書籍紹介:尾崎幸一『犯罪捜査の基礎になる考え方』(立花書房,1968年2月)
2022年06月17日読書メモ
50年以上前の本です。Amazonでは8万5000円という異常な高値がついていますが、3300円でまとめ買いした箱についていました。
内容は、警察大学校刑事教養部の教官である尾崎幸一氏が、警察庁の機関誌「第一線」などで書いた論文などを集めたものです。昭和43年2月20日初版発行で、私が入手したものは昭和60年12月20日初版第10刷発行となっています。
内容は平易ですが、先見性のある記述、鋭い着眼点が見られます。もちろん今の時点から見れば不十分な点も目につくのですが、50年以上前にこの域にたどり着いていたということに驚きました。
同時に、この本が増刷を重ねつつもすべての警察官に浸透したわけでもないのだろうなあという寂しさを感じました。もし浸透していれば、冤罪はもっと減っていたはずです。
以下、いくつか印象的な箇所を引用します。
9頁
【昔の捜査は、犯罪の嫌疑があれば、すぐに關置して取調べ、その供述(自白)によって証拠を集めるというやり方であった。だから留置取調べは捜査の出発点であって、關置取調べからいろいろの捜査がはじめられた。しかし、今日の捜査では、それが逆になっている。いろいろの捜査によって、証拠が集められ、それによって被疑者は逮捕されるが、その取調べは、それまでの捜査で収集した証拠によって認定されることが、真実かどうかをたしかめるというのが建前である。したがって、被疑者の逮捕は、捜査の出発点ではなくて終点である。だから、被疑者が弁解しなければ、捜査官の得た嫌疑の心証そのままを認めざるを得ないことになるのであって、これを弁解するかどうかは、被疑者の自由であり、それなればこそ、自己の意思に反して供述する必要はないことが、権利として認められる意味があるのである。】
32頁
【刑事訴訟法第三一九条第二項に、「被告人は公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定しているのはなぜであろうか。私の考えでは、それは、自白の強要を禁じて、人権を保護することもひとつの目的ではあろうが、もうひとつには、人の供述が証拠になるためには、そこに、何らかの欠陥があるからであろう、と思うのである。人の性能とか身体的機能には、欠陥があって、そうした体験を語る供述だけでは、真実の基準にできないからである。】
85頁
【私はどんな凶悪な犯人であっても、その犯罪をおかすのには、当人にとってやはりやむにやまれぬ事由があってのことだと考えるのである。少くともその犯人は自分自身ではそう思っていると思う。もちろん、それは世間で通用するような事由ではないかも知れない。しかし、そうした理由にもならぬ理由が、本人にとっては犯行におちいらざるを得ない大きな理由になっているのではないかと思われる…さきにも述べたように、われわれにも自分の目標獲得のためには、少しぐらいの法律違反をしてもかまわないという気持になるときがあるものである。誰でも、自分だけが聖人で、他人が徳低き者であるとさげすむことは許されないのである。この世の中に自分だけは犯罪者にはならぬと断言できる人がどれだけあるであろうか。もし、あったにしても、事実その人が犯罪におちいることがないという保障がどこにあろうか。彼もわれわれもともに同じ迷える羊であり、同病同憂の同行二人なのである。それは是非善悪の評価以前の人間性の問題ではなかろうか。捜査は、そうした人間性に立つところに、本当の道があるのではないかと私は思う。】
117頁
【行動環境の捜査 このようにして、人のなかに成立する心理学的環境には、客観的には同じ環境にありながら、各人各様にちがっていると考えなければならない。夏になって海に行く。海岸は誰にとっても海として、同じに認知されるが、しかしその認知を通じて、心の中に形づくられる心理学的環境にいたっては各人各様なのである。】
以上は昭和32年4月から33年5月に「第一線」で連載されたものです。
179頁
【犯罪捜査は、真実探究の過程である。それは科学における真実を探究する過程と本質的には同じである。…指紋の合致によって、犯人を断定し、血液型が合致したことによって、犯人と断定するようなことはないであろうか。もちろん、そのような科学的鑑定の結果が、極めて価値高いものであることはいうまでもない。しかし、それによって、犯人と断定するには、それだけでは不十分である。このことも、右述の捜査過程から見れば明白になるであろう。それは、事件の形態という面から考えれば、そのうちのほんの一部にすぎないのであって、仮説をたてる上の一資料にすぎないからである。捜査はその仮説についての験証を得て、仮説の真実性について高度の蓋然性が得られるまで高められねばならないのである。】