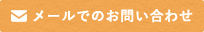裁判例紹介 高松高裁判決昭和四七年九月二九日高刑集二五巻四号四二五頁(不同意性交・不同意わいせつ)
2024年02月09日読書メモ
不同意性交・不同意わいせつの当罰性のコアは「同意しない意思(拒絶の意思)を形成、表明、全うできないことを利用しての性行為であること(性犯罪の本質的な要素が、自由な意思決定が困難な状態でなされたわいせつな行為であること)」です。表面的な「同意」の有無でも、「不同意」の有無でもなく、本人の真意を抑圧する状況があったか、それを作ったり、利用したか、が処罰のポイントです。実は、この点は改正前からまったく変わりません。一般の方や、警察において十分理解されていなかったというだけです。
このことは、裁判実務や学説では既にほぼ共通理解になっていましたが(後述の「高松高裁判決昭和四七年九月二九日高刑集二五巻四号四二五頁」はこの実質を明快に判示した先駆的な先例です。表面上は「女性から望んだ」事例で強姦罪の成立を認めています。)。現在でも示唆の得られる内容で、被害者代理人においても参考になるものだと思います。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/024472_hanrei.pdf
高松高等裁判所
昭和46年(う)第315号
昭和47年09月29日
理由
本件各控訴の趣意は、記録に綴つてある弁護人高橋英吉、同池田治共同作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
一 被告人Aに関する控訴趣意について
1 控訴趣意第一点(事実誤認の主張)について
(1) 原判示第二の(一)の事実について
論旨は、要すにる、原判決は、判示第二の(一)の項において、被告人Aは、「昭和四〇年一一月五日午後〇時三〇分ごろ、Bが同店において一五四円相当の商品を万引したことに因縁をつけ、強いて同女を姦淫しようと企て、同事務室において、同女に対し『あなたは一ぺんじやない何回も盗みをしちよるろう、ただじやすませんきに一時金として五、〇〇〇円出してくれ、五、〇〇〇円の金が一ぺんにできざつたら五丁目の警察へ突き出すぞ、お金ができんことは判つたが警察へ行くか、身体を張つたら今日のがは許しちやる、一回で五、〇〇〇円を精算してやる』などと申し向けて脅迫し、暗に右万引の事実を警察へ申告しないことの代償として情交関係を結ぶことを要求し、同女をして警察などへ申告され処罰を受けることなどに畏怖困惑の念を生ぜしめ、情交関係を結ぶもやむをえないものと思惟せしめ、もつてその反抗を抑圧し、同月一九日ころの午後一時三〇分ごろ、高知市a町b番地旅館『C荘』において強いて同女を姦淫した」旨の事実を認定しているが、(一)被告人Aは、前記Bが万引(窃盗)でつかまつた際、同女に対して「警察へ申告する。」と告げたことは、同被告人が真実捜査機関に申告する意思で窃盗犯人に告げたのであるから、何ら脅迫にあたらないし、よし、右行為が脅迫にあたるとしても、その時点においては、同被告人には強姦の故意がなかつたものであり、(二)かりに、同被告人が強姦の故意に基づいてBを脅迫したとしても、その脅迫は強姦罪の構成要件である相手方の反抗を抑圧する程度のものではなかつたのであり、(三)また、かりに、同被告人の前記脅迫が強姦罪における脅迫にあたるとしても、脅迫時(昭和四〇年一一月五日)と情交時(同月一九日)との間には一四日の日時の経過があり、その間Bとしては捜査機関に対し自己の犯罪事実とともに同被告人の脅迫行為を申告する時間的余裕が十分あつたのに、敢えてこれをしなかつたばかりでなく、かえつて三回にわたり同被告人に電話をかけて旅館まで指定して同被告人を誘い、しかもその旅館にはBの知り合いの仲居もおつて、Bは、同被告人から何らの暴行・脅迫を受けることもなく極く自然に同被告人と情交関係を結んでいるのであるから、前記脅迫と右情交関係との間の因果関係は切断されていることが明らかであり、右の情交関係は、要するに、同被告人が、万引をしたBに対して説諭をし、店員として働くよう勧めたことがきつかけとなつて、ホステスなどをして貞操観念の極めて低いBから、再三にわたり誘惑の電話を受けたので、これを承諾し、同女の合意を得たうえ情交関係を結んだものであり、強姦罪には該当しないのであつて被告人Aは無罪であるのに、これを有罪であると認定した原判決には事実誤認の過誤があるから、原判決は破棄を免れないというのである。
そこで、記録を精査し、当審における事実取調の結果を参酌して検討するに、原判決挙示の判示第二の(一)についての関係各証拠に、当審証人Bおよび被告人Aの当公判廷における各供述を総合すると、被告人Aは、日用雑貨・食料品などの販売を目的とする株式会社Dの代表取締役であるが、昭和四〇年一一月五日午後〇時三〇分ごろ、同会社の支店である高知市cd丁目「E」において、同店保安係Fが、代金一五四円に相当する同店の商品を万引したB(昭和一八年八月一〇日生)を現行犯人として逮捕し、その幼児二人(三才と二才)とともに同店三階事務室に連行したので、その取調に当り、ぶるぶる震えているBから万引した商品・預金通帳などの所持品を提出させ、氏名・年令・職業・住所などを質して始末書を書かせたうえ、約二時間にわたつて身上・経歴などの調査をしているうち、劣情を催し、同女を姦淫しようと決意し、「あなたは一ぺんじやない何回も盗みをしちよるろう。ただじやすませんきに一時金として五、〇〇〇円出してくれ、五、〇〇〇円の金が一ぺんにできざつたら五丁目の警察へ突き出すぞ。逃げたら警察へ言うぞ。短かくて一週間、長くて一ケ月は入らねばならぬぞ。」と申し向け、次いで同女の耳元に口を寄せて小さな声で、「a町ぢやつたら水商売をしよるろうが、お金ができんことは判つたが警察へ行くか、身体を張つたら今日のがは許しちやる。一回で五、〇〇〇円を精算してやる。あんたところはどの道を通つて行くか。」と申し向け、返事をしぶる同女に対し、さらに何回も「身体を張るか。警察を呼んでもええか。」とか「警察を呼んでもええよ。」と申し向けて回答を迫り、前記万引の事実を警察へ申告しないことの代償として情交関係を結ぶことを要求したこと、Bは、かつてGと婚姻し、前記の二児を儲けたが、その後右二児を引取つて事実上離婚した後、身体をこわし、生活保護を受けながら二児の養育にあたり、昭和四〇年一月ごろからHと同棲を始めたものの、一時金五、〇〇〇円を工面する資力はなく、幼児二人が階下で泣いており、もし警察に申告されれば処罰を受け幼児二人を残して刑務所に行かねばならないことになるかも判らないと畏怖し困惑の未、被告人Aと情交関係を結ぶのもやむを得ないと考え、同被告人に対し、「都合の良い日にお電話をします。」と承諾の返事をし、同被告人から同店の電話番号を教えてもらい、ようやく帰宅を許されたこと、Bは、帰宅後、同被告人の前記言動に思い悩み、同被告人との情交を拒絶するよい方法はなかろうかと案じ、これを顔見知りの警察官Iに相談しようと考え、その翌日高知警察署の受付を訪れたが、あいにく同人がいなかつたのでそのまま帰宅したものの、被告人Aに任所を知られており、また、同被告人から同被告人の要求に応じないで逃げれば警察に申告すると言われていたので、同被告人が自己の万引の事実を警察へ申告して今日にも警察官が家に来るのではなかろうか、そうなると内縁の夫Hにも万引の事実が知れ、また幼児二人を残して刑務所に入らなければならないと考え、びくびくした毎日を送つているうち、一時金を都合するあてもなく困り果てたあげく、遂に被告人Aに身体を許して精神的苦痛から抜け出し同被告人からのがれようと意を決し、同月一九日ごろ、同被告人に対し電話で身体を許すという趣旨の連絡をしたところ、同被告人から「これから行くが、どこがええか。」と言われ、自己の居住していたa町内にある旅館「C荘」に来てもらいたい旨答えたこと、被告人Aは、同日午後一時三〇分ごろ、前記C荘前附近で待つていたBを伴つて同荘二階客室に入り、女中に部屋代を支払つた後、Bが同被告人の前記言動によつて意のままになるのに乗じ、同室ベツトにおいて、同女を姦淫したこと、Bは、右姦淫終了後、被告人Aから「九」のつく日には前記支店に出勤しているから電話をしてくれと言われたが、それに対して明確な回答をしないまま同被告人より先に同旅館から立ち去り、同被告人に身体を許したことによつてすべてが解決したものと考え、その後同被告人とは何らの交渉もなかつたこと以上の各事実が認められる。証人Bは、原審(第一九回公判調書中の同証人の供述記載部分)および当審各公判廷を通じて、自己と被告人Aとの前記情交関係は、同被告人から脅迫を受けたことによるものではなく前記万引で同被告人から取調を受けたのがきつかけとなつて、自分が同被告人を誘惑し、合意のうえでのいわば売春である旨論旨に副う供述をするが、前記の各供述を仔細に検討すると、Bの右供述は、前後矛盾して一貫性がなく、同女の検察官に対すを供述調書および司法警察員に対する告訴調書の記載に照らしてとうてい信用できない。また、被告人Aの原審および当審公判廷における各供述中、前記認定に反する供述部分は、Bの検察官に対する供述調書に比較して信用できないし、他に前記認定を覆えすに足りる証拠はない。
以上説示の各事実によれば、被告人Aは、前記支店三階事務室において、Bの取調に当たつていた際、同女を姦淫しようと決意し、同女に対して前記認定のような内容の害悪を告知したことが明らかである。弁護人らは、右の脅迫は強姦罪における被害者の反抗を抑圧するに足りないものである旨主張するが、およそ、刑法一七七条前段の強姦罪にいわゆる脅迫は、被害者の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることをもつて足りる(最高裁判所昭和二四年五月一〇日判決、刑集三巻六号七一一頁。)と解すべきであるが、前記事実によると、被告人Aは、Bがぶるぶる震えながら万引の事実を素直に認めて謝罪し、万引した商品代金一五四円もその場で支払つたので、同女を万引の初犯者と認め警察へ申告する意思がなかつた(この事実は被告人Aの当公判廷における供述によつても明らかである。)のに、同女の弱身に付け込み、あたかも警察へ申告するような態度で、同女に対して、前記のとおり、「万引は一回でないだろう、一時金として五、〇〇〇円出せ、一時金を出さなければ警察へ申告する、警察へ申告すれば、短かくて一週間、長ければ一ケ月入らなければならない、警察へ行くか、身体を許すか。」と執拗に申し向け、同女に二者択一を迫り、もし自己に身体を許さなければ警察に申告することは必至であるような態度を示したのであり、その結果、同女をして刑事処分を受け同女の身体の自由・名誉などが害されるかもしれないと畏怖させたのであつて、しかも、その申告をするかどうかは、いつに被告人Aの意思にかかつていることを示していることが認められるのであり、これに加えて、前記害悪の告知された際の状況、Bの年令・経歴などをも合わせ考えると、前記脅迫は優にBの抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであつたと認めるのが相当である。
次に、前記認定の事実によれば、なるほど、論旨指摘のとおり、脅迫行為時と姦淫時との間には一四日間の経過があり、Bが情交当日被告人Aに同被告人との情交に応ずる旨の電話をした際、情交の場所を旅館C荘と指定しており、同旅館内での情交が外観上は極く自然とみられる状態において行なわれていることが明らかである。ところで、男女間で姦淫の行なわれるにあたり、事前に女子が男子に対し電話連絡をし、女子自ら姦淫の場所と時刻を指定し、その結果同場所で行なわれた姦淫も外観上は極く自然で通常の男女間の情交と認められるような状態においてなされているものであつても、前記場所等の指定および自然の状態で行なわれたかのように見える姦淫が、それ以前に加えられた犯人の脅迫行為によつて、被害者が精神的に抗拒する気力を失つた状態に陥り、その状態が継続していることによるものであつて、犯人が被害者のその状態に乗じ強いて姦淫した場合には、たとえ、脅迫行為時と姦淫時との間に一四日間の経過があり、姦淫行為が外観上は通常の男女間におけると同様な状態で行なわれたとしても、脅迫と姦淫行為との間の因果関係は中断されることなく存在するのであつて、脅迫による刑法一七七条前段の強姦罪が成立するというべきである。そこで、本件についてこれをみるに、被告人Aは、Bが万引でつかまり警察へ申告されるのをおそれているのに乗じ、同女に対し前記の脅迫を加えて同女を畏怖困惑させ、同女をして精神的に抗拒する気力を失わせる状態に陥しいれたうえ情交の承諾を余義なくさせ、その状態が続いている状況のもとで同女が被告人Aの指示に従い同被告人に電話をした際、同被告人の求めにより同女に情交の場所として旅館C荘を指定させ、次いで同旅館において同女が精神的に抗拒する気力を失つていて同被告人の意のままになるのに乗じて強いて姦淫の目的を遂げたのであるから、被告人Aの右一連の所為は、刑法一七七条前段の強姦罪にあたることが明らかである。
論旨は、被告人Aは、貞操観念の低い女性であるBから誘惑されたため合意のうえ同女と情交関係を結んだものであるとか、同女は、被告人Aから脅迫を受けた後、捜査機関に申告する時間的余裕があつたのに、敢えてこれをしないで、被告人Aを誘惑したものであると主張するが、当時Bが貞操観念の低い女性であつたとする原審第一九回公判調書中の証人Bの供述記載部分および当審証人Bの当公判廷における供述は、同人の検察官に対する供述調書の記載に照らして信用できないのであり、かりに、Bが貞操観念の低い女性であつたとしても、前記のような脅迫を加えたうえ強いて姦淫すれば強姦罪が成立することは言うまでもないことである。また、Bが捜査機関に対し被告人Aからの前記脅迫の被害を告訴しなかつたことは所論指摘のとおりであるが、同女は自己が万引したことを警察に知られることを最も怖れていたのであり、右脅迫被害を警察に届出ることは同時に自己の万引の事実を警察に申告する結果になることは明らかであるから、同女に対して右の告訴を強いることは自己の万引(窃盗)を自白させるに等しいことであり、被告人Aは同女の弱身に付け込んでの犯行であつて、精神的に抗拒の気力を失い思い迷つていた同女に対し右の告訴をしなかつたのを責めることは酷であるから、右の告訴がなかつた事実を捉えて、本件姦淫につき合意があつた証左とすることはできない。
そして、原判決挙示の関係各証拠を総合すると、原判示第二の(一)の事実は優に認められ、当審における事実取調の結果に照らしても、この結論を左右することはできない。従つて、原判決には所論指摘のような事実誤認の違法はないから、論旨は理由がない。
(2) 原判示第二の(二)の事実について
所論は、要するに、原判決は判示第二の(二)の項において、被告人Aは、「昭和四一年一月二三日午後四時三〇分ごろ、Jが同店において、四二八円相当の商品を万引したことで同事務室西側和室に連行されてきた際、右万引の事実に因縁をつけて強いて同女を姦淫しようと企て、同所において、同女の顔面を平手で二、三回殴打し、腹部を足蹴りするなどの暴行を加えたうえ、『今すぐ警察へ行くか、主人にもばらすぞ。』などと申し向けて脅迫し、更に同女の手を握り『俺のいうことを聞くか、警察や主人に言わないから、俺の言うことを聞け。』などと申し向けて暗に右万引の事実を警察や夫に申告しないことの代償として情交関係を結ぶことを要求し、同女をして警察や夫に申告され処罰を受けることなどに畏怖困惑の念を生ぜしめ、情交関係を結ぶもやむを得ないものと思惟せしめ、もつてその反抗を抑圧し、同年二月八日ごろの午後三時ごろ、同市ef番地ホテル『K』において、強いて同女を姦淫した」旨の事実を認定しているが、(一)被告人Aは、前記J。が万引(窃盗)でつかまつた際、同女に暴行を加えたのは大切な商品を万引されたことに対する感情的な激憤の余りであり、また同女に対して「警察へ申告する。」と告げたのは被告人Aが真実その意思で窃盗犯人に告げたのであるから、何ら脅迫にあたらないし、かりに、それが脅迫にあたるとしても、その時点においては、被告人Aに強姦の故意はなかつたのであり、(二)かりに、被告人Aが強姦の故意に基づいてJに暴行・脅迫を加えたとしても、その暴行・脅迫は強姦罪における相手方の反抗を抑圧する程度に足りないものであるし、(三)また、かりに、被告人Aの暴行・脅迫が強姦罪における暴行・脅迫にあたるとしても、暴行・脅迫時(昭和四一年一月二三日)と情交時(同年二月八日)との間には一六日の日時の経過があり、その間Jは、三回も被告人Aに電話をし、同被告人不在のときには事務員に同被告人の来社の日を尋ねるなどして同被告人を誘惑し、またホテルには別々に入り、ホテル客室では同被告人に入浴をすすめて自らホテル備付けの寝間着に着換え、ベツドの中ではキツスをするなど自由意思による情交関係と何ら変つたところはなかつたのであるから、前記暴行・脅迫と情交関係との間には因果関係が切断されていることが明らかであり、右情交関係は、要するに、被告人Aが、貞操観念の低いJから、三回にわたり誘惑の電話を受けたことによるものであつて、強姦罪にあたらないのであり、従つて被告人Aは無罪であるのに、これを有罪と認定した原判決には事実誤認がある、というのである。そこで、記録を調査し、当審における事実取調の結果を参酌して検討するに、原判決挙示の判示第二の(二)についての関係各証拠に被告人Aの当公判廷における供述を総合すると、被告人Aは、昭和四一年一月二三日午後四時三〇分ごろ、前記支店において、前記Fから、四二八円に相当する同店の商品を万引(窃盗)したJ(昭和一二年九月一日生)を現行犯人として逮捕して三階事務室西側和室に連行し、氏名、年令・職業・住所などを記載した始末書を提出させた旨の報告を受けるや、同女を姦淫しようと決意し、同室においていきなり同女の顔面を平手で二、三回殴打し、妊娠五ケ月の同女の腹部を足蹴りにするなどの暴行を加え、泣いて万引したことを謝罪する同女から住所・家族関係・経歴などを尋ねたうえ同女に対し、「今すぐ警察へ行くか、主人にもばらすぞ。」とか「警察を呼ぶぞ。」などと申し向け、次いで同女の手を握り、「俺の言うことを聞くか。警察や主人に言わないから俺の言うことを聞け。」と申し向け、前記万引の事実を警察や夫に申告しないことの代償として情交関係を結ぶことを要求したこと、Jは、最初に結婚した夫と別れた後、昭和四〇年三月ごろLと内縁関係を結び、当時妊娠五ケ月であつたが、被告人Aから前記万引の事実を警察へ申告されたり内縁の夫に告げられたりなどすると処罰を受けることになつたり内縁の夫から離別されることになるかもしれないと畏怖し困惑の末、同被告人と情交関係を結ぶのもやむを得ないと考え、同被告人に対し情交関係に応ずる旨の返事をしたところ、同被告人から日を指定されて、「今日は遅いので帰つてよいが、その日に電話をするように」と言われ同支店の電話番号を教えられて帰宅を許されたこと、Jは、帰宅後、被告人Aの前記言動に思い悩み、夜も眠れないような状態が続いたが、同被告人に住所も知られていたので困り果て、その二、三日後の被告人Aから指定された日の夕刻に電話をしたところ、既に同被告人は支店から帰つていなかつたが、事務員から、同被告人が怒つて帰つたことを聞き、同被告人の出勤日を聞いて電話を切り、再び同被告人の出勤日に電話をしたが、当日はJの内縁の夫が病気で休んでいたので、同被告人に都合が悪い旨告げたところ、同被告人から同年二月八日(ごろ)に電話をするよう指示されたこと、Jは、同月八日同市内三丁目の電車停留所附近の公衆電話で同被告人に電話したところ、同被告人が間もなく自動車を運転して同所に来たので、これに同乗し、同市ef番地ホテル「K」に向つたこと、被告人Aは、同日午後三時ごろ、Jを伴つて同ホテル客室に入り、女中に部屋代を支払つた後、Jが同被告人の前記言動によって意のままになるのに乗じ、同室ベワドにおいて、同女を姦淫したこと、Jは、右姦淫終了後、被告人Aから三月にも電話をしてくれと言われたが、その後は何らの交渉もなかつたこと、以上の各事実が認められ、右認定に反する被告人Aの原審および当審公判廷における各供述は、原審証人Jの供述(原審第九回第二〇回各公判調書中の同証人の供述記載部分)に照らして信用できないし、他に前記認定を覆えすに足る証拠はない。
以上説示の事実によれば、被告人Aは、前記支店三階和室において、Jを姦淫しようと決意し、同女に対して前記の暴行を加え、さらに前記認定のような内容の害悪を告知したことが明らかである。
弁護人らは、右暴行・脅迫は強姦罪における被害者の反抗を抑圧するに足りないものである旨主張するが、被告人Aは、Jに暴行を加えたので同女を警察へ申告する意思がなかつた(この事実は被告人Aの当公判廷における供述によつても明らかである。)のに、同女が万引をしてつかまつた弱身に付け込み、あたかも警察へ申告するような態度で、同女に対して、前記のとおり、「警察へ行くか、主人にもばらすぞ、警察を呼ぶぞ、俺の言うことを聞けば警察や主人にも言わない。」旨申し向け、同女に二者択一を迫り、もし情交関係に応じなければ警察に申告することは必至であるような態度を示したのであり、その結果、同女をして、刑事処分を受け、また主人にも告げられ、同女の身体の自由・名誉などが害されるかもしれないと畏怖されたのであつて、しかも、その申告をするかどうかは、いつに被告人Aの意思にかかつていることを示していることが認められるのであり、これに加えて前記害悪の告知された際の状況、Jの年齢・経歴などをも合わせ考えると、前記脅迫は優にJの抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであつたと認めるのが相当である。
次に、前記説示の事実によれば、なるほど、弁護人ら主張のとおり、暴行・脅迫の行為時と姦淫時との間には一六日間の経過があり、その間にJが被告人Aと情交関係を結ぶため三回にわたつて同被告人に電話しており、前記ホテル「K」客室での情交が外観上は極く自然にみえる状態において行なわれていることは所論のとおりである。しかしながら、被告人Aは、Jが万引でつかまり警察や同女の内縁の夫にその事実を申告されるのをおそれているのに乗じ、同女に対し、前記暴行・脅迫を加えて同女を畏怖困惑させ、同女をして、精神的に抗拒する気力を失わせる状態に陥しいれたうえ情交の承諾を余儀なくさせ、その状態が続いている状況のもとで三回にわたつて自己指定の日に電話をさせ、次いで同ホテルにおいて同女が精神的に抗拒する気力を失つていて同被告人の意のままになるのに乗じて強いて姦淫の目的を遂げたのであるから、被告人Aの右一連の所為は、原判示第二の(一)の事実について先に説示したと同様の理由により、刑法一七七条前段の強姦罪にあたることが明らかである。
論旨は、被告人Aは、貞操観念の低い女性であるJから三回にわたり誘惑の電話を受けたことにより情交関係を結んだものである旨主張するが、Jが貞操観念の低い女性であつたとする被告人Aの原審および当審公判廷における各供述は、前記証人Jの供述に照らして信用できないし、またJからの三回にわたる電話が論旨が指摘するような誘惑の電話でなかつたことは、前記認定のとおりであつて、右主張は採用できない。
そして、原判決挙示の関係各証拠を総合すると、原判示第二の(二)の事実は優に認められ、当審における事実取調の結果に照らしても、この結論を左右することはできない。従つて、原判決には所論指摘のような事実誤認の違法はないから、論旨は理由がない。
2 控訴趣意第二点(量刑不当の主張)について
論旨は、るる述べているが要するに、被告人Aを懲役三年の実刑に処した原判決の刑の量定は過重不当であるから、原判決は破棄を免れないというのである。
そこで、記録を調査し、当審における事実取調の結果を参酌して検討するに、被告人Aは、前記会社の代表取締役社長として同社の経営全般を掌理する立場にあつたのであるから、本件各被害者らの万引の事実を知り痛く憤慨したであろうことは容易に推測しうるところであり、本件各犯行に至る経緯がすべて各被害者らの不当な万引に端を発することを考慮すると、同被告人に対し同情するにやぶさかではないのであるが、しかしながら、同被告人は、前記会社の全従業員を指導監督する地位にありながら、原判示の「E」の品物を万引した木件各被害者らに対し、正当な法律手続によることなく、私利私欲を満たすため、いわば私的制裁ともいうべき方法により、各被害者らが万引をした弱身に付け込んで因縁をつけ、単独又は従業員と共謀のうえ、恐喝、強姦、傷害の本件各犯行に及んだものであつて、ことに、各被害者らはすべて女性であつて同女らの他聞をはばかる弱点に乗じた点は、その手段方法において極めて悪質であるというべく、社会に与えた影響も少なくないこと等その他記録に現われた諸般の情状にかんがみると、原判決が、被告人Aを懲役三年に処したのは十分首肯しうる量刑である。なるほと、所論指摘のように、原判示第二の(三)(四)の各傷害の程度は比較的軽いものであり、被告人Aは、原判示第一の(一)(二)、第二の(五)(六)の恐喝の各被害者であるM、N、OおよびPに対し、それぞれ喝取金額を弁償して同人らとの間に示談を成立させ、原判示第二の(三)(四)の傷害の各被害者であるQおよびRに対し謝罪をして同女らも被告人Aの厳罰を望んでいないし、原判示第二の(一)の強姦の被害者Sに対しては金三万円を支払い、同女も同被告人を宥恕しており、原判示第二の(二)の強姦の被害者Jに対しては金一〇万円を支払つて示談を成立させているが、犯罪により被害を蒙つたものにその損害の賠償をするのは当然であつて右程度の被害弁償がなされたからといつて特に刑を減軽するにはあたらないし、その他記録に現われた被告人Aの現在の心境、職業、社会的地位、経歴、家族関係など同被告人に有利な情状を十分斟酌しても、前記説示のような本件の各犯情に照らすと、同被告人が原判決程度の実刑処分を受けるのはやむをえないところであつて、これが過重不当であるとは認められない。従つて、論旨は理由がなく採用できない。
二 被告人Tに関する控訴趣意について
論旨は、要するに、被告人Tを懲役一年六月・執行猶予三年に処した原判決の刑の量定は、過重不当であり、原判決は破棄を免れない、というのである。
そこで、記録を調査し、当審における事実取調の結果を参酌して検討するに、被告人Tは、前記会社「E」の会計係員であるが、単独または被告人Aと共謀のうえ、原判示のとおり被害者らが万引をしたことに因縁をつけ、四回にわたり各被害者から現金を喝取したもので、その手段・方法は被告人Aについて説示したとおり悪質であることにかんがみると、原判決が被告人Tを懲役一年六月に処した量刑は首肯できるのであり、さらに、原判決が、同被告人は、前科がなく、従来真面目に働いてきたこと等その他原判決説示のような清状に照らして、三年間右刑の執行を猶予する旨の言渡をしたのであるから、原判決の右措置は相当であつて、さらに同被告人は、原判決言渡後各被害者に被害の弁償をしてそれぞれ示談を成立させるなどの誠意を示していること、その他記録に現われた同被告人の現在の心境、職業、家族関係などに照らして考慮しても、原判決が被告人を懲役一年六月・執行猶予三年に処した量刑が過重不当であるとは認められない。従つて、論旨は理由がない。
よつて、刑訴法三九六条を適用して、主文のとおり判決する。
第1部
(裁判長裁判官 木原繁季 裁判官 深田源次 裁判官 山口茂一)