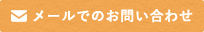飲酒後すぐの運転は酒気帯び運転にならないことがあります(道路交通法違反、刑事弁護)
2021年09月06日刑事弁護
理屈ではそうなるけど、良くこれを通したなという裁判例が判例タイムズに掲載されていました。飲酒後すぐの運転だったために「酒気帯び」にならなかったというものです。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=89859
【東京地方裁判所
令和1年(行ウ)第322号
令和02年07月03日
主文
主文
1 東京都公安委員会が平成31年4月14日付けで原告に対してした、運転免許取消処分及び1年間を免許を受けることができない期間として指定する処分をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実および理由
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は、原告が東京都公安委員会から酒気帯び運転をしたとして運転免許(以下「免許」という。)の取消処分(以下「本件取消処分」という。)を受けるとともに、1年間を免許を受けることができない期間として指定する処分(以下「本件指定処分」といい、本件取消処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことについて、酒気帯び運転の事実はないなどとして、それらの取消しを求める事案である。
(略)
3 前提事実
(1) 原告は、平成28年11月3日当時、中型自動車免許及び普通自動二輪車免許を有し、前歴は1回であった(乙1)。
(2) 原告は、平成28年11月3日午後4時30分頃、東京都(住所省略)所在のC店において、500mlペットボトルに25度の焼酎と水を約1:2の割合で入れた焼酎を飲み始め、そこから(住所省略)付近道路までの約1.6kmを普通自動二輪車で走行する間に、同ペットボトルの約3分の2の焼酎を飲んだ(乙5、9、10、弁論の全趣旨)。
(3) 原告は、平成28年11月3日午後4時35分頃、東京都(住所省略)付近道路において普通自動二輪車を運転していたところ、警察官から停止を求められ、(住所省略)先歩道上に停止した(争いがない。)。
(4) 原告は、平成28年11月3日午後5時02分から06分にかけて、水でうがいをした後、風船に呼気を吹き込み、北川式呼気中アルコール測定器DPA-11型に同風船を取り付けて呼気中のアルコール濃度を測定したところ、同日午後5時06分、呼気1lにつき0.16mgのアルコールが検出された(争いがない。)。
原告は、同日午後5時18分、測定結果を確認し、酒酔い・酒気帯び鑑識カードに署名指印した(乙5)。
(5) 東京地方検察庁立川支部検察官は、平成29年1月17日、原告の酒気帯び運転及び一時停止違反に係る道交法違反被疑事件を不起訴とする処分をした(弁論の全趣旨)。
(6) 東京都公安委員会は、平成29年6月9日、本件取消処分に係る意見聴取期日を開催したが、原告は、事前に欠席する旨を通知し、意見聴取期日に出頭しなかった(乙12、弁論の全趣旨)。
(7) 東京都公安委員会は、平成29年6月9日、原告が「酒気帯び運転(0.25未満)」を行ったものとして13点を付加し、これにより、原告の免許を取り消し、免許を受けることができない期間を1年間と指定する処分(本件各処分)をすることを内部的に決定し、本件各処分の処分書を交付するため、同日以降、原告に対し、複数回にわたって出頭通知書を郵送し又は電話を掛け、出頭を求めた。
原告は、平成29年12月22日、府中運転免許試験場に出頭したが、身分確認ができる運転免許証等を所持していなかったため、本件各処分の処分書を交付することができず、東京都公安委員会職員は、運転免許証を持参して再度出頭するよう依頼した。
東京都公安委員会は、平成30年5月23日、原告に出頭通知書を郵送して出頭を求めたが、原告は出頭しなかった。
東京都公安委員会職員は、平成30年6月10日、原告宅を訪問したが、原告は不在であり、本件各処分の処分書を交付することができなかった。
東京都公安委員会職員は、平成30年11月9日、原告の携帯電話に電話を掛けたが、原告は応答しなかった。
(甲1、乙1、13)
(8) 東京都公安委員会は、平成31年4月14日、府中運転免許試験場を訪れた原告に対し、本件各処分に係る同日付け運転免許取消処分書(甲1)を交付し、本件各処分をした(乙1)。
(9) 原告は、令和元年6月7日、本件訴えを提起した(裁判所に顕著な事実)。
4 当事者の主張
(原告の主張)
以下の理由により、本件各処分は違法である。
(1) 平成28年11月3日午後5時06分に呼気1lにつき0.16mgのアルコールが検出されたことは争わないが、呼気検査の時刻は、本来であれば運転を終え自宅で休んでいたはずの時刻であり、同日午後4時35分の運転中のアルコールの程度は立証されていない。運転時点では、呼気中アルコール濃度はそこまで高くなかった可能性がある。
(2) 「酒気帯び運転(0.25未満)」の成立要件である「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」とは、運転時に身体に保有されるアルコールが呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上が検出される状態であることをいう(以下「A説」という。)と解される。
(3) 違反行為があったとされる年月日から本件各処分まで2年5か月余りを要しており、少なくとも意見聴取期日の翌日には本件各処分を行うことが可能であったにもかかわらず、そこからさらに1年10か月余りを要しており、東京都公安委員会の事務処理遅延には合理的理由がない。
(中略)
第3 当裁判所の判断
1 前記「2 関係法令の定め」のとおり、施行令別表第2の1の表にいう「酒気帯び運転(0.25未満)」とは、身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態(身体に血液1mlにつき0.5mg以上又は呼気1lにつき0.25mg以上のアルコールを保有する状態を除く。)で車両等を運転することをいい、施行令44条の3は、道交法117の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度として、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mgと定める。
ここで、「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」の解釈につき、原告は、運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上(以下、血中アルコール濃度についての言及は省略する。)のアルコールが検出される状態である(A説)と主張するのに対し、被告は、運転時に体内にそれだけの量のアルコールを保有する状態であればよい(B説)と主張する。
A説によっても、運転時に呼気検査を行うことは現実的でないから、運転後の呼気検査の結果から運転時における呼気中アルコール濃度を推認することとなるが、A説は、それにより推認される運転時の呼気中アルコール濃度が呼気1lにつき0.15mg以上でなければ「酒気帯び運転(0.25未満)」は成立しないとするのに対し、B説は、運転後の呼気検査により呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールが検出されれば、運転後に追加して飲酒していない限り、運転時には、検査結果に対応するだけのアルコール量又はそれ以上のアルコール量が(消化器官に吸収され血液や呼気に反映される前であっても)体内に保有されていたのであるから、「酒気帯び運転(0.25未満)」が成立するとするものである。
しかし、施行令44条の3は、直接には道交法117条の2の2第3号の委任を受けて、犯罪構成要件の一部である運転時の身体におけるアルコールの保有状態として、呼気1lにつき0.15mg(以上)と定めているのであるから、運転時において呼気中アルコール濃度が上記の程度に達していることが酒気帯び運転罪の犯罪構成要件であり、また、道交法103条1項の委任を受けた政令で定める処分基準の内容となっているのであって、運転時に呼気中アルコール濃度が施行令44条の3で定める程度に達したとは認められないのに、運転後の呼気検査結果が上記の程度を超え、運転時において呼気又は血液以外の器官において同程度のアルコールを身体に保有していたことになるというだけで「酒気帯び運転(0.25未満)」が成立すると解釈する(B説)ことは、法令の文言を離れた不当な拡張解釈というべきであり、酒気帯び運転罪を構成し、処分基準にいう「酒気帯び運転(0.25未満)」を構成する「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」とは、運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールが検出される状態であることをいう(A説)と解するのが相当である。
実質的に考えても、道交法65条1項に違反する酒気を帯びた運転のうち、刑事罰や行政処分の対象となる酒気帯び運転を血液中又は呼気中のアルコール濃度が一定濃度以上のものに限定しているのは、交通事故発生の危険性を高める運転能力や判断力の低下は、胃や小腸から吸収されたアルコールが血管を通じて脳に作用する結果生じるものであることから、血液中のアルコール濃度を規制の基準とするのが合理的であり、さらに、その血液が肺に運んだアルコールが肺胞上皮に溶け込んで呼気となって排出されることから、呼気中アルコール濃度も酩酊の度合いを示すものといえるので、呼気中のアルコール濃度をも併せて規制の基準にしているものと考えられ、そうであれば、それらの規制値は、運転時に血中あるいは呼気中に存在し、現に運転能力の低下をもたらしているアルコール濃度を意味するものと解するのが相当であり、消化器官内にとどまりその後に血液内に入るアルコールをも評価の対象としているとは考え難い(このような道交法の趣旨からすれば、口腔中に残存する液体アルコールの影響により呼気検査で0.15mg/l以上の数値が検出されたとしても、それは血中アルコール濃度を反映した数値ではないから、施行令44条の3が想定する「呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態」とはいえない。捜査実務が呼気検査前に水でうがいをさせているのは、このような趣旨を踏まえたものである。)。
被告の主張のうち、上記説示に反する部分は採用できない。
2(1) 以上を前提に、本件における呼気検査結果から運転時の呼気中アルコール濃度が呼気1lにつき0.15mg以上であったことを推認できるかについて検討する。
一般に、飲酒後間もない時点までは、血中アルコール濃度は速やかに上昇し、最高濃度に達した後、上昇時に比して緩やかに下降し、このときの下降率はほぼ一定し、血中アルコールの消失曲線はほぼ直線となり、呼気中アルコール濃度もそれとほぼ比例することから、飲酒量から、一定時間経過したときの血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度をウィドマーク式算定法と呼ばれる計算式を用いて求められるなどとされている(乙20の1)。
(2) 公益社団法人アルコール健康医学協会のウェブサイトには、「アルコールは、胃や小腸から吸収され、血液に入り、循環されて脳に到達します。それまでに数十分かかります。」などと記載され(甲6)、厚生労働省のウェブサイトには、「体内に摂取されたアルコールは、胃および小腸上部で吸収されます。吸収は全般的に早く、消化管内のアルコールは飲酒後1~2時間でほぼ吸収されます。」、「飲酒後血中濃度のピークは30分から2時間後に現れ、その後濃度はほぼ直線的に下がります。」などと記載されており(甲7)、血中アルコール濃度及びこれに比例する呼気中アルコール濃度は、約30分から2時間後に最高濃度に達し、その後にほぼ直線的に下降する下降期に入るというのが一般的な医学的知見であると認められる。
本件において、原告の飲酒開始時刻は平成28年11月3日午後4時30分頃であることに争いがなく、本件全証拠によっても、当日、それ以前に原告がアルコールを身体に摂取したという証拠はない。
そうすると、その約32~36分後である同日午後5時02分から午後5時06分の間に呼気を風船に吹き込んだ時点では、原告の呼気中アルコール濃度は上昇期にあった可能性があり、運転時である同日午後4時35分頃の呼気中アルコール濃度は、呼気検査時よりも低かった可能性を否定できない。
したがって、下降期において呼気中アルコール濃度が経過時間に比例して低下するといった一般論に基づいて、本件における飲酒開始約35分後の呼気検査結果から、飲酒開始約5分後の運転時の呼気中アルコール濃度が同程度あるいはそれ以上であったと推認することはできない。
(3) ウィドマーク式算定法は、下降期の下降率がほぼ一定することから、飲酒直後の血中アルコール濃度が最大であるとして減少率に飲酒後の経過時間を乗じて一定時間経過後の血中アルコール濃度を推定する計算式であるから(乙20の1)、上昇期に適用することはできないものであり、上昇期であった可能性がある原告の運転時の呼気中アルコール濃度を推認するために用いることはできない。】
判例タイムズ解説(抜粋)
【3 「施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを身体に保有する状態」の意義
酒気帯び運転罪の成否に関し,「身体に施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを保有する状態」の解釈につき,運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールが検出される状態であるとする説(A説)と,運転時に体内にそれだけの量のアルコールを保有する状態であればよいとする説(B説)がある。経口摂取したアルコールはいったん消化器官等から血液中に吸収され,それが肺胞内に排出されて呼気に含まれるようになるのであるから,飲酒直後に運転し,しばらく時間が経ってから呼気検査を受けたような場合には,A説であれば,たとえ運転後の呼気検査により呼気1l中0.15mg以上のアルコールが検出されたとしても,運転時にそれだけのアルコールが検出されない可能性があれば酒気帯び運転罪は成立しないと考えることになるのに対し,B説は,運転後に追加して飲酒していない限り,運転時には,検査結果に対応するだけのアルコール量又はそれ以上のアルコール量が(消化器官に吸収され血液や呼気に反映される前であっても)体内に保有されていたのであるから,酒気帯び運転罪が成立すると考えることになる(以上につき,城祐一郎『Q&A実例交通事件捜査における現場の疑問〔第2版〕』〔立花書房,平成29年〕21~33頁)。
そして,飲酒開始の45分~1時間後,飲酒終了の約5分後に公訴事実記載の運転をし,その後の呼気検査で呼気1l中0.26mgのアルコールが検出されたという事案に関し,鳥取地裁平成3年4月25日判決(公刊物未登載)がB説に立って酒気帯び運転罪の成立を認めたのに対し,広島高裁松江支部平成4年7月20日判決(公刊物未登載)はA説に立って原判決を破棄し,被告人を無罪とした(城・前掲書28~32頁)。
飲酒開始の2~3分後に公訴事実記載の運転をし,その後の呼気検査で呼気1l中0.2mgのアルコールが検出されたという事案に関し,長野地裁伊那支部平成26年1月16日判決(公刊物未登載)は酒気帯び運転罪の成立を認めたのに対し,東京高裁平成27年1月9日判決(公刊物未登載)はA説に立って原判決を破棄し,被告人を無罪とした(城・前掲書22,26~28頁,木村昇一「飲酒した直後に車両の運転を開始してから2,3分後,酒気帯び運転の罪で検挙された事案について,検挙時刻までの被告人の呼気中のアルコール濃度は,政令で定める数値を下回っていた可能性を否定することはできないとして,無罪を言い渡した事例」研修805号63頁)。
本判決も,B説に立つ被告の主張を排斥し,A説に立って免許取消事由としての「酒気帯び運転(0.25mg未満)」は成立しないと判断したものである。
B説は,「身体に施行令44条の3に定める程度(呼気1l中0.15mg)以上のアルコールを保有する状態」に,「消化器官内に,その後に血液を通じて呼気に反映されれば呼気1l中0.15mg以上となるべき量のアルコールを保有する状態」が含まれると読むのであるが,余りに技巧的な解釈に思われる。
4 本件は,「施行令44条の3に定める程度以上のアルコールを身体に保有する状態」の意義につき,2件の刑事高裁判決と同旨の解釈により免許取消処分を取り消したものであるが,この論点に触れた文献は多くなく,また,刑事高裁判決2件も公刊物や主要な判例検索システムに登載されておらず,広く知られていないと思われるため,参考のため紹介した次第である。
(関係人仮名)】