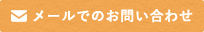【解決事例】勾留延長を回避して、早期釈放してもらいたいという相談
2024年01月28日刑事弁護
※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。
【相談】
Q、居酒屋で、たまたま居合わせた隣の席の客と口論になり、殴ってケガをさせてしまいました。早く釈放してもらいたいのですが、先日検察官から「勾留延長をする」と言われています。早期釈放してもらえないでしょうか。
A、弁護人から検察官や裁判官に意見書を提出する、あるいは準抗告をすることにより早期釈放が実現できる場合があります。
【解説】
以前私が取り扱った事例をモデルにしています。捜査機関に逮捕され、引き続き10日間の勾留がなされた場合、検察官は10日以内に公訴を提起しないときは被疑者を釈放しなければいけません。これが刑事訴訟法の原則です。しかし、残念ながら原則通りにいかず、「やむを得ない事由があると認めるとき」であるとして、さらに10日間勾留延長がされることがしばしばあります。これに対して弁護人がどう争うかですが、「検察官に勾留延長請求をしないように働きかける」「裁判官に勾留延長請求をしないように働きかける」「勾留延長請求決定に対して準抗告をする」といった手法が考えられます。どのような手法をとるかは事案によりますが、重要なことは、具体的な捜査手順を意識して、現実の捜査と比較して、主張を述べることです。抽象論で「やむを得ない事由がない」などと主張しても意味はありません。最高裁判例によれば、「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、事件の複雑困難(被疑者若しくは被疑事実が多数であるほか、計算複雑、被疑者関係人らの供述その他の証拠の食い違いが少なからず、あるいは取調べを必要と見込まれる関係人、証拠物等が多数ある場合等)、あるいは証拠収集の遅延若しくは困難(重要と思料される参考人の病気、旅行、所在不明若しくは鑑定等に多くの日時を要すること)等により、勾留期間を延長して更に取調べをしなければ起訴、不起訴の決定をすることが困難な場合をいう(最判昭和37年7月3日民集16巻7号1408頁)とされていますので、その場合にあたらないことを主張していく必要があります。
※刑事訴訟法
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20231215_505AC0000000066#Mp-Pa_2-Ch_1-At_208
【参考意見書】
勾留延長請求に対する意見書
福岡地方裁判所刑事部 御中
(福岡区検察庁に副本提出)
弁護人 鐘ケ江 啓 司
上記被疑者に対する傷害被疑事件被疑事件につき、意見を述べる。
記
第1 請求の趣旨
被疑者に対する勾留延長請求を却下する
との決定を求める。
第2 請求の理由
1 はじめに
本日、検察官から御庁に対して勾留延長請求がなされていると思われる。
私は、本意見書作成時点で検察官と話ができていないので、推測ではあるが、検察官は、「関係人取調べのため」「引き当たり捜査未了」「示談交渉につきその成否を確認しなければ当該事件の適正処分を決しがたい」「被害者の傷害期間が確定していない」「被害者取調べ未了」「被疑者取調べ未了」「裏付け捜査未了」といった理由で勾留延長請求をしてくるものと思われる。
しかし、本件ではいずれも勾留延長理由にはなり得ず、勾留延長請求は認められない。
2 既に勾留の理由と必要性が消滅していること
本件において特徴的なことは、被疑者について〇月×日以降取調が一切行われておらず、引き当たり捜査も行われていないことである(資料1・被疑者ノートの写し)。本件のように単純な傷害事件においては、通常であれば、勾留期間中に被疑者の取調べは終了しており、引き当たり捜査も行われているはずである。ところが、それがなされていない。
一方、被疑者が釈放されないことで、被疑者のみならず被疑者の会社関係者、被疑者の妻には多大な不利益が生じており、これらを解決するためには被疑者の釈放が不可欠な状況に至っている(資料2・被疑者作成の裁判官宛文書、資料3・被疑者の妻からのメール、資料4・従業員からのメール)。勾留の必要性も消滅している。
勾留延長の決定にあたっては勾留の理由と必要性が存在することが必要であることから、既に勾留の理由と必要性が欠如している本件では勾留延長は認められない。
3 「やむをえない事由」が存在しないこと
勾留延長が認められるのは、「やむを得ない事由があると認めるとき」である(刑事訴訟法208条2項)。
「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、事件の複雑困難(被疑者若しくは被疑事実が多数であるほか、計算複雑、被疑者関係人らの供述その他の証拠の食い違いが少なからず、あるいは取調べを必要と見込まれる関係人、証拠物等が多数ある場合等)、あるいは証拠収集の遅延若しくは困難(重要と思料される参考人の病気、旅行、所在不明若しくは鑑定等に多くの日時を要すること)等により、勾留期間を延長して更に取調べをしなければ起訴、不起訴の決定をすることが困難な場合をいう(最判昭和37年7月3日民集16巻7号1408頁)。
しかし、本件においては、必要な捜査は完了しているか、仮に必要な捜査が残っていたとしても、それは捜査機関の怠慢によるものである。勾留延長は認められない。
(1)「事件の複雑困難」について
本件は、そもそも被疑者が、居酒屋でたまたま隣席に居合わせた被害者を殴打等して全治2週間の怪我を負わせたという単純な事例であり、複雑困難な事案ではない。
検察官は、被疑者が犯行に至った経緯、犯行状況について、被疑者が一部につき「記憶にないけど、相手が言うならそうだと思う」といった回答をしていることをもって、事件が複雑困難でありさらに取り調べをしなければ起訴・不起訴の決定ができないと主張するものと思われる。
しかし、被疑者は勾留決定の当初より「一応被疑事実を認める旨の供述をしている」と評価されているところであり(令和×年(む)第×号、同第×号、同第×号)、自白に準じて考えられる状況である。勾留延長をしてさらに取り調べを行うことは起訴・不起訴の判断には不要である。
さらに、実務上、当初の勾留期間に捜査を遂げなかったことが相当でないと考えられる場合や、被疑者・関係人の供述が食い違っていても、その重要度や各供述の信用性の軽重等も考慮すると、さらに取調べや裏付け捜査をする必要性に乏しい場合は、勾留延長請求を却下するものとされているところ(資料5・飯畑正一郎「勾留期間を延長すべきやむを得ない事由の意義」別冊判例タイムズ34号174頁)、本件では被疑者と被害者の言い分について食い違いがあるとしても、当初の勾留期間に捜査を遂げておくべき事項であるし、改めて取り調べをする必要性に乏しい事案というべきである。
被疑者は、一度たりとも黙秘も、取り調べ拒否もしていない。一般に、被疑者が黙秘・否認していることを理由に勾留延長をすることすら、自白を得るために身柄を拘束することになり、許されないとされているところ(上掲飯畑論文174頁)、虚偽の自白をせず、正直にしゃべっている被疑者が、被害者の言い分と完全に一致する供述をしていないという理由をもって勾留延長することはなお許されいない。このような勾留延長が許容されるのであれば、被疑者に虚偽自白を強要することになる。
被疑者が正直にしゃべっていることは、被疑者にとって有利な事実(酩酊している被害者に暴言をはかれた)ことについても記憶がない旨供述していることから明らかである。被疑者ノートにも警察の取調べに正直に回答していることが記載されている。
事件の複雑困難を理由とする勾留延長は認められない。
(2)「証拠収集の遅延若しくは困難」について
被疑者の携帯電話についても、捜査機関に押収されて1週間以上が経過している。被疑者はパスコードも隠しておらず、正直に説明している。既に被害者にいては十分な取り調べがなされる時間的余裕はあったはずであり、証拠収集が遅延する理由はない。
本来であれば、本件は〇月□日時点には捜査が完了できる事案だったのである。
本件で安易に勾留延長をするということは、捜査機関の都合を被疑者に押しつけるものでしかない。捜査の遅延が捜査機関の責めに帰すべき場合であって、証拠収集の遅延若しくは困難を理由とする勾留延長請求は認められない。
以下では、具体的に検察官が勾留延長請求の理由としてくると考えられる事項に沿って、反論を加える。
(3)「関係人取調べのため」について
検察官は、被疑者に同行していたXの取調べや、店員からの事情聴取が必要ということで、勾留延長請求をしてくることが考えられる。
しかし、Xについては、本意見書作成時点で一切警察から連絡がなされていない(資料6・Xの電話聴取書) 。この時点で、そもそも取調べの必要性がないか、あるいは勾留延長請求の材料にするためにあえて連絡をしていないものと考えられる。また、飲食をした店については、福岡市中心部の店なのであるから、福岡県中央警察署の人間であれば容易に事情確認にいけるはずである。当然済まされているはずであるし、済ませていないのであれば、捜査の怠慢である。勾留延長理由にはならない。
(4)「引き当たり捜査未了」について
被疑者については、いまだ引き当たり捜査がなされていないようである。しかし、〇月×日から〇月△日までは取調べもなく、引き当たり捜査をする時間的余裕は十分存在した。捜査の怠慢であり、勾留延長理由にはならない。
(5)「示談交渉につきその成否を確認しなければ当該事件の適正処分を決しがたい」について
示談交渉については、示談交渉をするための金銭的準備ができておらず、交渉の開始ができないところである。この点は、〇月×日付の検察官宛「終局処分(中間処分)に関する意見書」にて詳しく説明をしたところである。
傷害罪の示談交渉にあたっては、暴行罪の場合と異なり、慰謝料のみならず、治療費、休業補償、通院交通費の支払義務も生じるところであるが(資料7・服部啓一郎ほか『先を見通す捜査弁護術犯罪類型編』147頁)、とりわけ被害者も会社経営者であることから100万円を越えることは当然に想定される。また、適正な損害額については、早くとも被害者の治療が終了して職場復帰できた段階でなければ算定できない。そのため、弁護人は前任の検察官に対して、処分保留釈放を求めるとともに、それができないのであれば罰金刑での終結(示談不可を前提の処分)を求めていたところである。
勾留延長をしたところで、現状では示談が成立しないことが明白なのであり、勾留延長請求の理由にはならない。
(6)「被害者の傷害期間が確定していない」について
検察官は、被害者の傷害期間が確定していないことを理由に、勾留延長を求めてくることが考えられる。
確かに、当初の診断書では全治2週間の怪我とされていても、それが延びることはあり得ることである。しかし、だからといってこれが被疑者を拘束する理由に直結するものではない。被疑者が、被害者の受診する医療機関を探し出した上で、虚偽の診断書を出すように働きかける、といったことは不可能である。また、延長したからといって治療期間が確定できるとも限らない。
被疑者の怪我の程度が確定していないことは勾留延長事由にそもそもならないか、あるいは勾留延長期間内に捜査を遂げる見込みがあるともいえないため、勾留延長請求の理由にはならない。
(7)「被害者取調べ未了」について
検察官は、被害者の取調べが未了として勾留延長を求めてくることが考えられる。しかし、本件においては、逮捕状・勾留状請求のために事件発生直後から集中的に被害者の供述調書は取られているはずである。また、被害者は〇月×日時点では退院できるほどに回復していたのであり、取調べに困る状況でもなかった。捜査員が出張して取調べをすることもできたはずである。
被害者に対するさらなる取調べはそもそも不要か(せいぜい電話聴取で足りる)、仮に取調べが必要だとしても行われていないのは捜査員の怠慢に過ぎない。勾留延長請求の理由にはならない。
(8)「被疑者取調べ未了」について
被疑者取調べ未了については、そもそも取調べ目的の勾留延長請求は認められないところであるし、冒頭で述べたように、〇月×日以降に被疑者の取調べはなされていない。
勾留延長請求の理由にはならない。
(9)「裏付け捜査未了」について
その他、検察官は被疑者の飲酒量について裏付け捜査が必要といったことを主張するかもしれない。
しかし、被疑者は多量の飲酒をしていたことも正直に供述しており、携帯電話も任意に提出しているところである。捜査に積極的に協力しており、犯行態様についても重要な情状についても捜査は尽くされているはずである。これ以上の裏付け捜査が必要な事案ではない。終局処分にとって枝葉末節の部分について捜査する必要があるといった理由で、勾留延長請求をルーズに認めてはならない。
傷害罪において重要な情状について、吉田誠治(最高検察庁検事)は次のとおり説明している【傷害罪は、暴行罪と同様に身体に対する罪であるが、傷害という結果が発生している点が加重要素となっているものであるから、後記の暴行罪の情状(記載例16.解説(1) : 346頁参照)のほかに、傷害の軽重(傷害の部位、程度、 内容、後遺症の有無等。記載例19.解説(3) : 355参照)、傷害の故意の有無が情状として重要となる。】【暴行罪は、身体に対する罪の一つであり、情状として重要な点は、 まず暴行の態様、すなわち、単に素手で殴ったものであるか、道具を使用した犯行かといった暴行の具体的内容、暴行の部位・回数・執勘さの程度等であるが、 そのほかに、犯行の動機も重要となる。犯行の動機との関係では、暴行罪や傷害罪は、被害者側にも犯行を誘発する落ち度があったり、被害者も被疑者に暴行を加えていることが少なくないので、被害者側の言動や暴行の有無等についても捜査し、被疑者の犯情に影響するものについては、記載しておく必要がある。また、 この種事犯は、被疑者の激情的性格や飲酒が大きく影響していることがあるし、暴力団関係者による暴行あるいは傷害については、 当然のことながら厳しく対処する必要があるので、 これらの点についても漏れなく記載すべきである。】(資料8・吉田誠治『新版補訂5版 記載例中心 事件送致の手引』(東京法令出版、2019年6月)343~346頁)。
これらの重要な情状に関する捜査は既になされているか、少なくともなされているべきことであり、勾留延長請求の理由にはならない。
(10)結論
本件においては、そもそも勾留延長をする必要性がない上に、仮に被害者や被疑者の取り調べ等が必要であったとしても、それは当初の勾留期間に行うべきことであった。
「やむを得ない事由」はなく、勾留延長は認められない。
4 捜査完遂の見込みがないこと
本件については、弁護人が把握している捜査の状況からすれば、被疑者と被害者の取調べをする必要性がある、という点を検察官は勾留延長の理由として強調してくるものと思われるので、特に付言する。
勾留延長については、勾留を延長すればその期間内に捜査を遂げる見込みがあることも必要である(前掲飯畑論文174頁)。
しかし、本件では、被疑者には一部の記憶が欠けているところ、捜査を遂げる見込み、すなわちこれが解消される見込みというのは存在するのであろうか。
本件では、被疑者が被害者を殴った際の目撃者はおらず、勾留を延長したところでどちらかの言い分が正しいということを裏付ける客観的証拠がでる見込みはないのである。そして、被害者については少なくとも今より記憶が鮮明な時期に取り調べがなされていると思われるところ、検察官や警察官が改めて取り調べをすることによりその供述内容が変更されるものであろうか。それも、被疑者にとって有利に変更されるものであろうか。被害者の言い分は十分に聴取されているはずであって、今さらこれが変更されるということ自体が不自然である。
そして、被疑者も素直に供述して、調書が作成されているのであって、勾留取消請求においても自ら作成した誓約書や陳述書で罪を認めているのである。被害者宛の謝罪文も作成している(資料9・被害者宛謝罪文)。普通に考えれば現在の供述内容が変更されるとは考えがたい。そうすると、両者を取り調べたところで本来溝は埋まらないはずである。
唯一、言い分の食い違いが解消される見込みがあり得るとすれば、被疑者が、身体拘束が継続される不利益に耐えかねて、虚偽自白をすることで被害者の言い分と一致するということである。
勾留が続き、一日でも早く釈放されたい被疑者にとって、虚偽自白をすれば早期の処分が得られるかもしれないというのは極めて抗いがたいものである。被疑者に前科がなく、傷害罪であっても罰金刑または執行猶予判決に留まることが予想される本件ではなおさらである。
しかし、そのことをもって、勾留延長をすれば捜査が完遂される見込みがあるなどと判断することが許されるはずがない。
本件において、勾留延長をするということは、被疑者に虚偽自白を強いるということにほかならない。仮に捜査の必要性があるとしても、在宅捜査で十分なのであって、勾留延長は相当でない。
この点、近時の裁判官の論文で、被疑者が黙秘する場合には、翻意して供述をはじめるという見込みがない限り、捜査完遂の見込みもない、との指摘がなされていることを述べておきたい(資料10・片岡理知「捜査と準抗告-準抗告の裁判例からみた勾留期間延長又は鑑定留置の必要性・相当性-」河上拓一編著『刑事手続法の理論と実務』230頁)。本件でいえば、被疑者の供述内容が被害者の言い分に沿って変更される以外に言い分の不一致が解消される見込みがないのであれば、捜査完遂の見込みはないのである。
そして、身体拘束の不利益を課して虚偽供述を強いる以外に供述変更の見込みがない(在宅捜査ではできない)というのであれば、そもそも勾留延長してはいけないのである。
5 勾留取消請求等がなされたことは勾留延長の理由にならないこと
なお、これは検察官も主張してこないと考えられるが、一部において、弁護人が勾留取消請求や勾留理由開示請求をしたことが勾留延長の理由になり得るとする見解も見られるところであるので付言する。
資料11・河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法第二版第4巻〔第189条~第246条〕』(青林書院,2012年4月)483頁には【勾留中に,被疑者側から,勾留理由開示,勾留取消しの請求,人身保護請求等の手続がとられる場合がある。これらの手続がとられたことが,当然に勾留延長の理由となるものではないが,順次これらが申し立てられた場合には, これに必要な時間,捜査が妨げられる場合があり, このような場合,延長の理由として考慮される場合もあり得よう(宮下・逐条解説81頁)】との記載があり、資料10の231頁でも引用されているところである。
しかし、大コンメンタールで引用されている文献は、コピー機が存在しない昭和24年の文献であり(宮下明義・新刑事訴訟法逐条解説II (昭24司法警察研究会公安発行所))、現在ではそのまま妥当するものではない。そして、弁護人は、勾留理由開示請求や、人身保護請求など、被疑者の身柄を移動させる手続はとっていない。しかも、本件は複雑な事件で捜査記録は容易にコピーできる量である。さらに、勾留取消請求のタイミングは日曜日夜、金曜日夕方と、捜査の妨げにならないタイミングで行っており、実際に月曜日は被疑者の取調べもなされている。
万一、検察官が弁護人から勾留取消請求等をなされたために捜査が進まなかった等の主張が出た場合は、それが真実であるかどうかしっかり吟味されたい。
6 まとめ
被疑者には勾留の理由も必要性も消滅している上、勾留延長を正当化する「やむを得ない事由」もない。勾留延長請求は却下されるべきである。
弁護人は本日予定を終日空けているので、勾留延長審査を担当する裁判官との面談を希望する。いつでも連絡されたい。
なお、本意見書と添付資料については、公平な審理を実現するため、検察庁にも本日コピーを提出している。
以 上
【参考判例】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52899
判示事項
一 刑訴第二〇八条第二項所定の「やむを得ない事由があると認めるとき」の意義
二 検察官が勾留延長請求をし裁判官が右請求認容の裁判をするについて、国家賠償法第一条第一項所定の過失があるとした原判決が違法であるとされた事例
裁判要旨
一 刑訴第二〇八条第二項所定の「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、事件の複雑困難(被疑者もしくは被疑事実が多数であるほか、計算複雑被疑者関係人らの供述その他の証拠のくいちがいが少なからず、あるいは取調を必要と見込まれる関係人、証拠物等が多数の場合等)、あるいは証拠蒐集の遅延もしくは困難(重要と思料される参考人の病気、旅行、所在不明もしくは鑑定等に多くの日時を要すること)等により、勾留期間を延長して更に取調をしなければ起訴、不起訴の決定をすることが困難な場合をいうものと解すべきである。
二 原判決挙示の事実関係だけでは、検察官が勾留延長請求をし裁判官が右請求認容の裁判をしたことをもつて、直ちに国家賠償法第一条第一項所定の過失があるとはいえない。