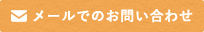喧嘩闘争と正当防衛(暴行・傷害、刑事弁護)
2024年02月16日刑事弁護
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
刑法上、「正当防衛」行為については、犯罪が成立しないものとされています。もっとも、「喧嘩闘争」の場合は正当防衛でないとされることも多いです。その区分について、いくつか文献を調査しましたので紹介します。喧嘩闘争として正当防衛が否定されるのは、侵害の事前の予期により急迫性が欠如する場合と積極的加害意思の存在による防衛の意思が欠ける場合に大別されます。
① 橋爪隆「第2章相互闘争状況をめぐる判例理論の検討 第1節「喧嘩と正当防衛」をめぐるわが国の判例の動向」『正当防衛論の基礎』(有斐閣,2007年5月)
【(1) 侵害の予期の有無とその程度
(a) 侵害の予期が欠ける場合
喧嘩闘争の一コマのようにみえても, 防衛者が相手方の侵害を予期していない場合がある。もちろん,およそ侵害があることなど想像してもいなかったような状況で一方的に相手の攻撃を受けたような場合は,そもそも喧嘩闘争とはいい得ないであろう。しかしながら,ある程度の侵害を受けることは覚悟して喧嘩に臨むような場合であっても,個別の侵害内容については具体的予期が欠ける場合がある。このような場合について,戦前の判例は基本的に正当防衛・過剰防衛を肯定している。】(123頁)
【さらに,侵害の予期があったか否かは必ずしも明らかにされていないが,職場の同僚に注意をくわえたところその暴行を受けるに至った事例(大判昭8.4・10刑集12巻437頁),松茸泥棒を誰何したところ, その暴行を被った事例(京都地判大10 ・12・19新聞1928号10頁)について, それぞれ過剰防衛,正当防衛が認められている。これらの場合,かりに被告人の挑発行為と評価しうる行為が先行しているとしても, それは正当な行為であり, 非難されるべきものではないことが重要であるように思われる。】(130~131頁)。
【本節においては,大審院時代から最近の下級審裁判例に至るまで, 「喧嘩と正当防衛」をめぐる判例の動向について検討を加えた。その結果, 多少の揺らぎはあるものの, わが国の正当防衛に関する判例の態度には, 明らかな連続性を見いだすことができた。
まず第一に,正当防衛の制限において,侵害の事前の予期が重要な意義を有している点である。たしかに最高裁昭和52年決定は「当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても, そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではない」と明言している。しかし本決定も,侵害の予期に加えて,積極的加害意思が認められる場合には正当防衛の成立を排除しているのであるから,侵害の予期が正当防衛排除の前提要件として機能していることは否定し得ないのである。もっとも,侵害の予期がなぜ正当防衛論において重要な意義を有しているのか, その理由は必ずしも明らかではない。この点については,侵害の事前回避義務がそもそも,また,いかなる場合に認められるのかという問題に関連して,さらに理論的検討が必要となろう。また,判例が事前の加害意思・攻撃意思を重要視していることも,大審院判例以来,裁判実務における一貫した態度である。侵害の予期も含めて,侵害に先行する時点における行為者の意識内容が,正当防衛の成否において決定的なファクターとなっているということができよう。これに対して,不正の侵害を引き起こすに至った客観的事実経過は,要件論のレベルでは重要ではないようにみえるが,実際には,積極的加害意思の存否を判断する情況証拠として重要な意義を有している。換言すれば,積極的加害意思肯定例・否定例は,客観的な事実関係から類型化することも, ある程度可能である134)。
このように事前の意識内容が重要な意義を有するのに比して,防衛行為者の対抗行為時点における主観面は,正当防衛の成否にとって,あまり重要な意義を有していない。わが国の判例は大審院以来,一貫して防衛意思必要説に立脚しているが,その要求水準はそれほど高度なものではない。したがって,喧嘩闘争の場面において相手方の重大な侵害に対時しているような場合には,ほとんどの場合に防衛意思が認められている。逆に防衛意思が否定されるような場合は,そもそも正当防衛の客観的成立要件が欠ける場合がほとんどであり,行為者の主観面が決定的な基準となって,正当防衛の成立が否定されているわけではない。】(177~178頁)
② 山口厚「正当防衛論の新展開」法曹時報61巻2号(2009年2月号)
【すなわち,正当防衛が「権利行為」だということの意味は,それが法文上「自己又は他人の権利を防衛するため」のものであることに示されているように,法的に認められた正当な「椎利」の防衛手段であり,侵害を排除しうることはそうした「権利」の内容そのものだということである。つまり,正当防衛が「権利行為」であるのは,防衛対象の「権利」性に由来するものと理解されるべきなのである。このような意味においてこそ,正当防衛は「権利行為」である。このようにして,正当防衛は,不正、違法法な侵害と正当な権利とが対立する場面において,正当な権利に優越的な地位を認め, それを保護するものとして認められているのである。そこから, 「正は不正に譲歩する必要はない」との原則が導かれ,不止な侵害を受ける者にはその侵害から退避することが求められないことになる。こうして, 「権利行為」としての正当防衛においては,退避義務が存在しないことになるのである。正当防衛においては, このようにして認められる退避義務不存在の原則を確認することがまずもって大切であるといえよう。】(23~24頁)
【確かに,侵害者の生命に危険をもたらす反撃行為については,防衛行為の相当性などの要件の慎重な検討が必要であるが,上記の考えでは,不正な侵害者の(かけがえのない)生命保護という理念により,正当な権利者保護という正当防衛の基本的趣旨が没却されてしまいかねないように思われる。仮に被侵害者の利益のみを考慮し,侵害者の利益を考慮しないことが問題だとしても, 今度は侵害者の生命の重要性が強調され,侵害の脅威にさらされた被侵害者の正当な権利が無視される結果となってしまっているのではなかろうか。これは,逆の意味で,行き過ぎであり,問題であろう。そのような結論に至る元の原因は,権利である被侵害法益と不正な侵害者の利益とを同じレベルで扱っているところにあり,それによって,侵害者の行為が不法なもので,被侵害者こそが守られるべき正当な権利者だという基本的認識がいつの間にか忘れ去られてしまっているところにあるように思われるのである。「現場に滞留する利益」に言及するとしても,それはいわば一種の比嶮的表現であり,それは,権利者の優越性という意味において, まさしく「一般的・制度的な利益」として把握される必要があるといえよう。】(26~27頁)
③西田典之著・橋爪隆補訂「正当防衛」『刑法総論[第3版]』(弘文堂,2019年3月)
【(iv) 侵害の創出(自招侵害) さらに,侵害が現在しても, なお急迫性を否定すべき場合がある。それは,正当防衛の趣旨,制度的理由から,急迫性が否定されるべき場合である。正当防衛にも,違法な攻撃者と防衛者との法益の衝突がある。これを利益衝突状況と呼ぼう。そして,正当防衛とは。違法な攻撃をした者の責任・負担において利益衝突状況を解消するという法制度である。とすれば,利益衝突状況を作り出した者=侵害の創出者が正当防衛権を行使することは否定されるべきであろう。その代表的な行為が挑発行為(自招侵害)である。甲が乙に喧嘩をしかけておいて, 乙が攻撃するのを待ちかまえて反撃する行為は,反撃の時点だけとってみれば正当防衛にあたるとしても, その原因が甲にある以上,すでに述べた回避義務の原則から、正当防衛は認められないのである。判例が,従来から,喧嘩両成敗として喧嘩について正当防衛を認めない傾向にあるのも, このような考え方にもとづくものである(最大判昭和23 . 7 . 7刑集2巻8号793頁〔128〕, ただし, 最判昭和32 . 1 .22刑集11巻1号31頁(129] をも参照)。】(172頁)
④ 中尾佳久「最高裁判所判例解説刑事編 最判平29・4 ・26刑集71・4・275」
【最高裁は,喧嘩闘争と正当防衛に関して,早い段階から,先行事情を含めた行為全般の状況をみて,正当防衛の成否を決すべきとの考え方を示している(昭和23年判例)。これは,先にも述べたが,客観的には,法益侵害の危険が間近に差し迫っていたとしても,正当防衛が,急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに,侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものであることから,対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況を総合的に考慮し,行為者の取った対抗行為が刑法36条の趣旨に照らし例外的に許容されるものとはいえない場合には,対抗行為を違法と評価し,正当防衛を成立させないというものと解される。昭和23年判例は,喧嘩闘争と正当防衛に関する重要な視点を示したものであり,喧嘩闘争類型の正当防衛成否に関する基本的な考え方はここにあるように思われる。
そして,その後の判例理論は,昭和23年判例の考え方を背景に,具体的な判断基準を個別類型ごとに示してきたものとみることができると思われる。
すなわち,積極的加害意思論を示した昭和52年判例は, 「単に侵害を予期していたにとどまらず,積極的加害意思がある場合には,侵害の急迫性が否定される」との命題を示したが,それは,行為者の「意思内容」に着目した上で,行為者の取った対抗行為が緊急状況に対処するためのものとして例外的に許容されるものとはいえない一つの場合を示したものと理解することがで(注17)きると思われる。
本決定も, このような理解の下で、昭和52年判例が示した積極的加害意思論は,侵害の急迫性が否定される一つの場合であるとの位置付けを明らかにしたのではないかと考えられる。
(略)
また,本決定は,最高裁として刑法36条の趣旨を初めて明らかにしたものと思われるが,その内容は,正当防衛が緊急行為としての違法性阻却事由に当たることを明らかにするものであり,正当防衛の成立範囲に変更をもたらす新たな解釈を示すものとはみられない。
このように,本決定は,急迫性を否定する範囲を拡大して正当防衛の成立範囲を狭める方向性を示すようなものではないことに留意すべきである。】(110~111頁)
⑤橋爪隆「第4草正当防衛状況の判断について」『刑法総論の悩みどころ』(有斐閣,2020年3月)
【昭和52年決定の理解においては,急迫性の判断において侵害の予期が大きな役割を果たしていることが重要である。「予期された侵害を避けなかったというにとどまらず, その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき」という表現からは,本決定が予期された侵害の存在を前提として,積極的加害意思の存否を問題にしていることが窺える。したがって侵害の予期が認められない場合には, そもそも積極的加害意思の存否の検討に立ち入るまでもなく(時間的な切迫性が認められる限り)侵害の急迫性が肯定されることになる7)。
3.積極的加害意思の内容
それでは積極的加害意思とは具体的にどのような意思内容なのか。明確な定義が示されているわけではないが, 昭和52年判例は,被告人が「相手の攻撃を当然に予想しながら,単なる防衛の意図ではなく,積極的攻撃, 闘争,加害の意図をもって臨んだ」という事実から積極的加害意思を肯定していることから,積極的加害意思を認定するためには,攻撃,加害目的が必要であり, 防衛目的,護身目的の場合には積極的加害意思は否定されると理解することができる8)。もっとも,正当防衛とは,相手に対する加害行為によって自らを防御する側面を有しているため, 防衛目的と加害目的の区別はかなり微妙なものにならざるを得ない9)。】(81頁)。
⑥ 幕田英雄「正当防衛(その1)侵害の「急迫性」と「防衛の意思」-喧嘩闘争における正当防衛の成否一」『捜査実例中心刑法総論解説(第3版)』(東京法令出版,2022年10月)
【1 喧嘩闘争の意味
(1) 攻撃・防御の立場の違いが明白な場合
正当防衛が成立する典型的場面としては、例えば、侵害者が相手を待ち伏せして攻撃を開始し、これに相手が応戦した場合のように、侵害者がまず攻撃意思を抱いて相手への攻撃を開始し、相手がこれに対して専ら防御的に反撃を開始するといった事態が思い浮かぶ。この場合は、攻撃・防御の立場の違いが明白であり、防御的立場でこの事態に巻き込まれた相手(被侵害者)に正当防衛が成立するとすることに何ら跨跨は生じない。
(2) 喧嘩闘争の場合
しかし、相互に攻撃防御を繰り返すいわゆる喧嘩闘争においては、互いに相手に攻撃を加えようとする意図で闘争に臨んでいることが多く、闘争参加者中の攻撃者と防御者の区別ははっきりとはつかない。例えば、会社の同僚AとBの喧嘩闘争があったとして、この両者の間に喧嘩闘争が始まるまでには、①普段からの不和関係→②その場での不和あつれき状況→③口論→④有形力の行使というプロセスがあり、③の口論までの段階において、A、B両者ともに、相手を積極的に攻撃したいという意思(喧嘩の意思)ができあがっているのが通常である。確かに④の有形力行使が開始される場面においては、A, Bいずれが先に手を出したかという形式的意味で、どちらが先制的であったかという区別は付くが、その両者のいずれが攻撃的で、いずれか防御的であったかということは容易に判断できない。
④の有形力行使の場面のたまたまある時点でA, Bの一方が防御状態であったとしても、それは攻撃・防御を繰り返す闘争の過程のうちの一時的なものにすぎないのであり、全体としてみれば、やはり、いずれが攻撃者でいずれが防御者であるとはいいにくいのである。】(291~292頁)
⑦ 前田雅英ほか編「刑法36条」『条解刑法〔第4版補訂版〕』(弘文堂,2023年3月)
【7) 喧嘩と正当防衛 喧嘩に正当防衛を認める余地があるかという問題がある。一般的にいえば,喧嘩は, それ自体社会的相当性を欠く行為である上,昔から「喧嘩両成敗」などといわれているように,本来的に正当防衛の観念になじみにくい性質を有している(現に大審院の判例は,喧嘩両成敗の法理により正当防衛の成立を否定していた)。したがって,喧嘩につき正当防衛の成否が問題となる場合には,事態を全体的に観察して判断する必要があり, 闘争行為中の瞬間的な部分的攻防だけを切り離して判断してはならない(最大判昭23.7.7集2-8-793)。部分的には防衛行為の様相を呈していたとしても,全体的に観察する限りにおいては, その行為も全体としての攻撃行為の一環をなしている場合が少なくないであろう。侵害の急迫性が防衛行為を正当とする状況上の前提要件であることに鑑みると.喧嘩の多くは,侵害の急迫性の要件を欠き,正当防衛の成立が否定されるものと思われる。しかし,喧曄についても防衛行為性を認める余地が全くないわけではない(最判昭32.1.22集ll-1-31)。例えば,初めは素手で殴り合っていたのに,突然相手がナイフを持ち出して攻撃してきた場合や,喧嘩の途中から行為者が喧嘩の意思を放棄し攻撃を中止しているにもかかわらず, 相手がなお一方的に攻撃を続けた場合など, 中途から侵害の急迫性を肯認し得る場合などがこれに当たる。事態を全体的に観察する態度を忘れないとともに, 自招侵害(本条注6)等を念頭に置きつつ, 個々の行為につき急迫性の要件の存否等を慎重に検討することが必要である。】(126頁)