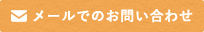正当防衛における防衛行為の相当性(刑事事件)
2024年02月16日刑事弁護
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
刑事弁護において、正当防衛の成否が問題となる事例では「防衛行為がやむを得ずした行為」か、換言すれば「防衛行為が相当なものであったか」が問われます。緊急避難の場合のような補充の原則は要求されないので、必ずしも「必要最小限」というものではなく、必要かつ相当なものであることで足り、それが唯一の方法であったことは要件になりません。この点につき、文献を調査しましたので紹介します。
①川口宰護「最高裁判所判例解説刑事編 最判平元・11 ・13刑集43・10・823」
【思うに、最高裁の判例においては、既に触れたように、二四年判決が、「防衛行為が巳むことを得ないとは、当該具体的事態の下において当時の社会通念が防衛行為として当然性、妥当性を認め得るものを言う」と判示しており、それは、大審院時代からの一貫した考え方に基づくものであること(注15)、また、四四年判決が、刑法三六条一項の「巳ムコトヲ得サルニ出テタル行為」の意義を判示するに当たり「すなわち」という言い替えの文言を間に入れたうえ「反撃行為が……防衛手段として相当性を有するもの」としていることからすれば、四四年判決も、基本的にはそれまでの判例の考え方に従ったものと理解できよう。ただ、正当防衛においては、不正な侵害者についても、その生命、身体等の法益が法的保護を失ったわけではなく、防衛者が権利を防衛するために出た行為に侵害者の法益を超える重要性が認められるため、侵害者に対する反撃行為を違法と評価しないにすぎないこと(注16)からすれば、防衛行為の内容、程度は、防衛者が権利を防衛するために必要かつ十分なものでなければならないと解される。四四年判決が「巳ムコトヲ得サルニ出テタル行為」とは、「反撃行為が……防衛する手段として必要最小限度のものであること」としたのは、このような趣旨を示すためであったと考えられる(注17)。
しかしながら、他面、四四年判決が判示した「防衛する手段として必要最小限度のものであること」を余り強調し過ぎると、正当防衛の成立範囲を不当に狭く限定することになりかねない。特に、正当防衛においては緊急避難の場合のような補充の原則は要求されておらず、また、防衛行為が不正な侵害行為に対するとっさの場合の自己保存行為であることを考えると、四四年判決の趣旨も、防衛行為が、侵害行為に対する反撃行為として考えられる種々の方法の中で妥当なものであったと認められれば足り、厳格な意味での必要最小限度の手段までをも要求したものではないと理解するべきものと思われる(注18)。
本判決が、被告人の行為を刑法三六条一項の「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に該当すると判示するに当たり、それが「防衛する手段として必要最小限度」内のものであるかどうかについて格別触れなかったのは、四四年判決がした前記定義付けを否定する趣旨ではなく、むしろ、右のような考え方を背景にして、「防衛手段としての相当性」につき判断すれば足りると解したからではないかと推察される。
…(注一八)四四判決の事案をみると、被告人は、Tと押し問答をしていた際「Tが突然被告人の左手の中指および薬指をつかんで逆にねじあげた」のに対し、「痛さのあまりこれをふりほどこうとして右手で同人の胸の辺を一回強く突き飛ばし」たというものであるが、被告人としては、Tからねじあげられている左手を手前に強く引くとか、横に振るとかして、Tの攻撃を排除することもできたのではないかと思われる。そうだとすると、右判決においても厳格な意味での必要最小限度までは要求されていなかったと考えられよう。】(343~344頁)
②橋爪隆「刑事裁判例批評(130)最高裁平成21年7月16日第一小法廷判決」刑事法ジャーナル21号(2010年2月号)
【もっとも、必要な防衛手段の認定において、過去の先行事情が、事実上、影響を及ぼすことは考えられる。すなわち本判決においても、妨害行為が執拘に繰り返されていた事実によって、侵害者側の侵害意欲がきわめて強固なものであり、説得・交渉等のより穏便な手段によって侵害を回避することが期待できない(少なくとも、被告人がそのような手段を試みる義務はない)ことが示され、それによって、被告人の即座の実力行使を正当化するという関係が認められるように思われる。】(88頁)
③増田啓祐「最高裁判所判例解説刑事編 最判平21・7 ・16刑集63・6・711」
【過去の侵害に対する正当防衛が認められないように,防衛行為が相当であるか否かは,現在の侵害との関係で決せられるべきものであって,本判決がこれまでのBらの行為に言及したことの理解が問題となる。この点, Bらの本件侵害行為は,本件看板を取り付ける行為にすぎず,直ちに被告人らによる本件建物の使用収益を物理的に不能にしたり, F宅建の業務を直接妨害したりするものでないことにも照らし,当該行為だけを切り取って見れば,その侵害の程度は軽微であるかのようである。しかし,本件におけるBらの侵害行為とこれに対する被告人の防衛行為は,単純な喧嘩事案のように,本件当日偶発したものではなく,従前の経緯の上に行われたものであって,その点を抜きにしては, Bらの本件侵害行為等,ひいては本件紛争の実態を正当に評価できないように思われる。すなわち, Bないしその勤務するE不動産は, これまで,被告人らの本件建物の使用収益等本件建物に対する権利等を種々の手段で妨害してきたところであり,本件建物への看板取付行為に限っても, これまで七,八回にわたり繰り返してきたところである。このようなBないしE不動産の従前の妨害行為は,本件侵害行為に係る意思の強固さや執ようさ等を推認させる事情ということができ, このような事情がない場合に比べ,本件侵害の程度がより強度であるとの評価を導き,防衛行(注11)為の相当性を肯定する要素となり得るものと考えられる。】(303頁)
④岸洋介「正当防衛に関する近時の判例の動向及び捜査実務上の留意点」捜査研究2015年7月号(773号)
【ここでは,本判決が取り上げた防衛行為の相当性の点について.本判決の判断枠組み及び背景にある考え方を検討します。
ア本件侵害行為について
本判決で注目されるのは, 「Bらは,(中略)本件建物のガラスを割ったり作業員を威圧したりすることによって被告人らが請け負わせた本件建物の原状回復等の工事を中止に追い込んだ上,本件建物への第三者の出入りを妨害し, (中略)即時抗告棄却決定の後においても,立入禁止等と記載した看板を本件建物に設置するなど,本件以前から継続的に被告人らの本件建物に対する権利等を実力で侵害する行為を繰り返しており,本件における上記不正の侵害はその一環をなすものである。」と判示して、Bらによる本件以前の被告人らに対する同種の妨害行為について言及していることです。
本件におけるBらの侵害行為は,本件建物に本件看板を取り付ける行為にすぎず, これによって直ちに被告人らによる本件建物の使用収益を物理的に不能にしたり, F宅建の業務を直接妨害したりするものではありませんから, この行為だけを切り取って見れば,その侵害の程度は軽微であるようにも思われます。しかし,本件におけるBらの侵害行為とこれに対する被告人の防衛行為は,単純な喧嘩闘争の事案のように, 本件当日に偶発的に起こったものではなく,従前から続く経緯の延長線上で行われたものであり, この点を抜きにしては, Bらの本件侵害行為の程度ひいては本件紛争の実態を正当に評価できないように思われます。
ただし,過去の侵害に対する正当防衛は認められませんから,防衛行為が相当であるか否かは,現在の侵害との関係で決せられなければなりません。それゆえ, Bらが従前から被告人らに対して本件侵害行為と同種の妨害行為を繰り返していたという事実は,本件侵害行為自体の侵害意思の強固さや執ようさ等を推認させる事情として捉えることができ,このような事情がない場合と比較すると,本件侵害の程度はより強度なものと認められると解するのが相当です。本判決が, 「本件における上記不正の侵害はその一環をなすものである」と判示しているのも,このような趣旨から,過去の経緯等について言及したものと理解することができます(注6)。】(9~10頁)
⑤中川博之「正当防衛の認定」木谷明編著『刑事事実認定の基本問題[第3版]』(成文堂,2015月11月)
【正当防衛の場合は, 「不正」対「正」の関係にあることから, その防衛行為が唯一の手段であることは必要でないし(すなわち補充の原則の適用はない),厳格な法益の均衡も要求されない。】(150頁)
【この点で,いわゆる「武器対等の原則」は,主として攻撃防御の場面において,相当性の判断基準として重要な指標を提供するものである46)oこれまで裁判例の多くは「武器対等の原則」に従って相当性の有無を判断しており,①素手による攻撃に対して素手で反撃した場合,②凶器による攻撃に対して素手又は凶器で反撃した場合には相当性が認められることが多く,③例外的に,他の行為を選択することについて期待可能性がない場合にも相当性が認められるとされている。】(151~152頁)
⑥高野隆・河津博史「第14章 最終弁論」『刑事法廷弁護技術』(日本評論社,2018年2月)
【ここで、正当防衛ということについて、少し考えてみたいと思います。われわれはみな、神から与えられた命を全うし守る権利があります。他人が理不尽な暴力をふるってきたとき、われわれは自分の生命や身体を守るために、反撃する権利があります。たとえその反撃の結果、相手が死んだとしても、われわれは罪に問われることはありません。これが正当防衛です。この正当防衛の権利はすべての人に平等に保障されています。性別や職業や社会的身分に関係なく、すべての個人は、自分の命と健康を守るために不正な攻撃に立ち向かう権利が保障されているのです。
前科や前歴のある人には正当防衛の権利がないというようなことがあってはなりません。正当防衛というのは、不正な攻撃に対する反撃でなければなりません。ですから、反撃に名を借りて、攻撃のための攻撃をすることは許されません。例えば、相手が自分を攻撃してくることを予想して、ナイフを持って相手を待ちぶせして、相手が来たらそのナイフで切りつけるなどということは許されません。しかし、相手が攻撃を仕掛けてきたときに、相手の攻撃力を冷静に分析してそれに見合う程度の攻撃しかしてはいけないということはありません。そもそもそんなことは不可能です。街を歩いていて突然酔っ払いから「この野郎、ぶっ殺してやる」と怒鳴られ、殴りかかられたら、皆さんはどうしますか。そのときに、どの程度の力で殴ったらいいのかなどと考えている余裕はありますか。ありません。私なら、潭身の力を振り絞って相手を殴ることしかできません。1発殴ってもダメなら2発でも3発でも殴るでしょう。その結果相手が死んでもそれは正当防衛です。われわれには相手の攻撃力を分析する義務などありません。相手の攻撃から逃げる義務もありません。われわれは相手が理不尽な攻撃をしてきたら、その場に立ち止まり、反撃する権利があるのです。
佐藤さんは、Fマートでタバコを買い、家に帰って所属タレントが出演するテレビ番組を見る予定でした。その予定は完全に狂ってしまいました。なぜか。自宅の150メートル手前で、鈴木さんに出会ってしまったからです。飲み過ぎて店の中で大声で怒鳴り声を上げ、他の客にも迷惑をかけていた客は、ついにママさんからボトルを取り上げられ、店から追い出されました。佐藤さんはその男に、因縁を付けられ、体当たりをされ、首を掴まれたのです。それでも佐藤さんは冷静に対処しました。
男を振り払って自宅に向かいました。ところが、その男は佐藤さんに2度目の攻撃を仕掛けてきました。今度は、本格的にファイティングポーズをとって、左右の拳で連打してきました。佐藤さんは両腕でガードし、男のパンチを振り払いました。それでもなお、男はパンチを繰り出し、蹴りを入れてきました。佐藤さんは間合いをとるために、前蹴りをしましたが、決して手を出しませんでした。最後の最後、男が大きく振りかぶって来たとき、パンチを出しました。相手のパンチよりも先に佐藤さんのパンチが相手に当たりました。もしも、これが正当防衛ではないというのなら、正当防衛などという制度はやめてしまった方がいいでしょう。】(298~300頁)
⑦東京高判平成30年3月30日D1-Law.com判例体系〔28262081〕
【所論は、被告人が、まともに攻撃も防御もできないCに対して、一方的かつ強度の暴行を加えており、被告人の本件暴行が防衛の程度を著しく超えたものとして過剰であることは明らかであり、かつ、被告人にはその認識があったことも明らかである、という。
確かに、被告人による本件暴行は3回にはおよそとどまらないという意味で多数回にのぼるものである。また、それらにより、顔面や下顎部に相当数の傷害を生じさせており、本件暴行は、相応に強い力によるものであったといえる。とりわけ、下顎部に対する暴行により、下顎部の〓開創、舌骨骨折、椎骨動脈裂創が生じており、特に椎骨動脈裂創は、前記のとおりCの首が過伸展して生じたもので、被告人によるCの下顎部に対する殴打は相当強かったというべきである。さらに、Cは、飲酒の影響により、知覚能力等が相当低下していたことなどから、被告人による殴打を十分防御できず、攻撃をしても被告人に傷害を負わせることができなかったため、Cのみが顔面に多数の創傷を負う結果となっている。
しかし、被告人は、本件暴行中もCから攻撃を受け続けており、本件暴行時に手加減できなくても、やむを得ない面がある。また、被告人は、Cの攻撃に対して、素手で反撃するにとどまっている。そして、被告人は、Cが転倒した後(おそらくは、致命傷となった下顎部への殴打により転倒したものと考えられる。)、Cの胸倉をつかんでいるものの、Cを殴打したり、足蹴にしたりするなどの暴行を加えていない。さらに、被告人がCよりも12歳若いものの、身長はCとほぼ同じで、体重はCより約10kg軽いことが認められ、被告人とCとの間で、体格等において顕著な差があるとはいえない。
これらの事情に照らすと、被告人による本件暴行が正当防衛として許された防衛の程度を超えていたとは断定し難い。】
⑧中村明日香「実務刑事判例評釈[Case322] 札幌地判平12.3」警察公論2019年8月号
【もっとも,防衛行為の相当性を判断するに当たり考慮される事情の中には,侵害行為の急迫性の緩急や侵害行為の強度等が含まれているように(前記4(3)ア参照),防衛行為が相当といえるか否かの判断は, 「急迫不正の侵害」がどのようなものであったのかという点と連動する,すなわち,侵害がより押し迫っていたというような急迫性の程度がより高い状況であった場合や,侵害がより強度であった場合には,そのような侵害に対する防衛行為として相当といえる行為の範囲は,より広いものとなると考えられる。】(94頁)
⑨松井芳明「防衛行為の相当性○最判平元・11 ・13刑集43・10・823」植村立郎編『刑事事実認定重要判決50選(上)《第3版》』(立花書房,2020年3月)
【もとより,急迫不正の侵害に対する反撃行為であればどのようなものであっても許されるわけではなく, 防衛行為として相当性を有するものに限って許されるにすぎない。それでは, どのような場合に相当性を有するのであろうか。過去の事例において相当性を有するとされたものとそうでないとされたものとを分析検討した結果,「武器対等」といえる事例においては相当性を有し,「武器対等」とはいえない事例においては相当性を有しないと判断される傾向にあったことから,それが相当性を有するか否かを判断するいわば1つの基準となり、論者によっては「武器対等の原則」とも呼ばれるようになった。これは,一般的には妥当な結論を導くものであり,有用な基準であるといえるが,本件のように防衛行為者が侵害者よりも体力的に劣り素手で防衛する余裕のない場合や,裁判例7のように防衛行為者と体力的に劣らない侵害者が素手とはいえ相当執勧な攻撃を加えてきた場合のように,形式的に「武器対等の原則」を当てはめると不当な結論を招いてしまうこともある。そこで,一般的には妥当な基準である「武器対等の原則」を修正する必要が生じる。すなわち、「武器対等の原則」が妥当するのは防衛行為者と侵害者との間に体力的な差がさほどなく, かつ, 防衛行為者が素手で防衛する余裕のある場合であり, そのような前提が崩れている事案においては, 防衛行為者が凶器を用いたとしても, それだけでは直ちに防衛行為の相当性を欠くとはいえず,他の事情も考慮して相当性の有無を判断する必要がある。そのような場合であっても,裁判例8のように防衛行為者が侵害者に対しいきなり刃物で突き刺すなどの攻撃に及んだような場合は相当性を有するとはいい難いであろうが,本件のように, 防衛行為者が刃物を構えて「切られたいんか。」などと言ったにすぎないという消極的な用い方にとどまるような場合や,裁判例7のように, 刃物で攻撃を加えたとしても侵害者に対する積極的・意図的な反撃行為ではなく, その回数も侵害者の攻撃に比して過剰とはいえないような場合には,形式的には「武器対等」とはいえないものの,実質的にはなお「武器対等」であるというべきであろう。また, 凶器の用い方のほか,他に取り得る手段があったか否かという事情等も考慮する必要があると思われる。】
⑩幕田英雄「正当防衛(その2)防衛行為の相当性一正当防衛と過剰防衛一」『捜査実例中心刑法総論解説(第3版)』(東京法令出版,2022年10月)
【2身体・生命に対する素手による侵害に、素手で反撃した場合
この場合は、双方の体力・力量に著しい差がない限りは、双方は武器対等と考えられ、防衛行為としての相当性の範囲内にあるといえる。
なお、相手が酩酊している場合には、酩酊者は運動能力が低下していることが考慮されることがある。】(313頁)
※民事事件における「正当防衛」の相当性に関する文献も紹介します。民事事件においては、刑法上の「緊急避難」も正当防衛に含まれますので、やや記述が異なっています。
①平井宜雄「三 正当防衛」『債権各論Ⅱ不法行為法』(弘文堂,1992年4月)
【「自己又ハ第三者ノ権利ヲ防衛スルタメ已ムコトヲ得スシテ」なされた加害行為であることという要件のうち、「已ムコトヲ得スシテ」とは①加害行為をする以外に適切な方法がないこと、②「他人ノ不法行為」から防衛される法益と正当防衛によって侵害された法益との間に社会観念上ほぼ合理的な均衡が保たれていること、を必要とする旨説かれている
(略)
②に関しては、正当防衛の対象たる不法行為者について生じた法益侵害の場合とそれ以外の第三者について生じた法益侵害の場合とを区別し(『民法修正案理由書』の前記引用箇所を参照)、不法行為者に生じた被侵害利益に関しては、防衛された利益との合理的均衡を考える必要はないと解すべきである。すなわち、不法行為者は正当防衛を誘発した者であるから、それに対しては法益の合理的均衡を失していても正当防衛が成立しうるが、正当防衛の招来に何ら責のない第三者に対しては、②で述べた合理的法益均衡の要件を加重することのほうが、バランスのとれた、かつ比較法的にも支持される解釈だと考えるべきである】(95~96頁)
②潮見佳男「第三章 防衛目的での不法行為」『不法行為法Ⅰ〔第2版〕』(信山社,2009年9月)
【③防衛のための加害行為がやむをえないものであったこと この要件は,加害行為の必要性と相当性の意味で理解することができる。この要件は,過剰介入禁止の要請から付加されるべきであり,主に,防衛される権利・法益と侵害された権利・利益との均衡(法益の均衡)が問題とされる。この要件を欠いた過剰防衛については,責任阻却の効果は認められない。もっとも,過剰な防衛行為が同項にいう「他人」に対してされた場合には,過失相殺の対象となりうる4.】(452頁)
③佐伯仁志・道垣内弘人「第12回自救行為(2)」『刑法と民法の対話』(有斐閣,2001年5月)
【佐伯 先ほど申し上げたように、民法の正当防衛の中には刑法で緊急避難とされている場合が含まれているわけですから、必ずしも民法が「不正からは逃げよ、正に対しては譲歩する必要なし」ということになっているわけではないでしょう。民法の先生の中でも、例えば、四宮和夫先生は、七二○条一項の場合でも、第三者の法益の侵害は、本来は正当防衛ではなく緊急避難として正当化すべきものであり、したがって、第三者の法益を侵害する場合における違法性阻却の成否は、第三者への避難行為の場合と同じに取り扱うべきではないだろうか、と述べておられます(四宮和夫『不法行為』三六八頁(一九八三年)))】
④藤岡康宏「第3節違法性阻却事由のある場合」『民法講義Ⅴ不法行為法』(信山社,2013年3月)
【第3に,加害行為は「やむを得ず」行われたものでなければならない.
同旨の表現は刑法36条(正当防衛)および37条(緊急避難)にもあるが, 36条にある「急迫不正の侵害」にあたる要件は民法には存在しない. しかし,やむを得ない行為の判断基準については,民法上も急迫性が必要であるとされ,これを含む3つの基準,急迫性,補充性および法益均衡性があげられている.
すなわち,-
①危険の発生源に急迫性があったこと,すなわち,他人の違法行為を原因
とする緊急状態の発生に急迫性があったこと(急迫性の原則).
②他人(または第三者)に対する権利侵害(または法律上保護される利益の侵害)が行われる以外にほかに適切な手段がなかったこと(補充性の原則).
③防衛利益(720条) と被侵害利益(709条) との間の均衡がいちじるしく失われていないこと(法益均衡の原則).
正当防衛が認められている以上,法益均衡は対等である必要はないが,権利防衛手段としての均衡, その意味での合理的均衡が保たれていることが必要である(13.
なお,法益均衡が失われると,過剰防衛となり,権利侵害の違法性は阻却されない.加害者は損害賠償の責任を負う(ただし,過失相殺による減額は可能である).】(149~150頁)
⑤平野裕之「不法行為責任の成立を阻却する事由」『民法総合6 不法行為法〔第3版〕』(信山社,2013年6月)
【(b) 「やむを得ず加害行為をした」こと正当防衛が認められるためには, 「やむを得ず加害行為をした」ことが必要であり, この意味は,①加害行為をする以外に適切な方法がなく,かつ,②防衛される法益と侵害される法益との間に,社会通念上の合理的な均衡が保たれていること(防衛行為の相当性),を必要とすると考えられている(②を超えると過剰防衛)362。例えば,暴力団関係者に絡まれたが,逃げる可能性が十分あったのに,腕に覚えがあったので,いい稽古とばかりに殴って重症を負わせた場合には,正当防衛にはならない(①欠如)。また,正当防衛が許される場合にも,防衛のための加害行為の程度は必要な限度に止まるべきであり,殴りかかられてこれを避けるために蹴りを入れてかわしたが,そのまま逃げればよいのに,蹴りを何発か入れて重症を負わせるというのは,過剰防衛であり責任は否定されない(②欠如)。但し,いずれの場合も,相手が原因を作っているので,大幅に過失相殺がされるべきである。なお,防衛意思も違法性阻却のためには必要になる。】(211頁)
⑥吉村良一「4 違法性阻却事由」『不法行為法〔第6版〕』(有斐閣,2022年8月)
【正当防衛は,やむをえずなした行為であることが必要である。具体的には,他に方法がなかったこと,守るべき権利(利益)とそのためになした行為により侵害された利益の間に社会的に見て合理的な均衡が保たれていることが必要である。なお,この点の判断にあたっては,侵害された利益が攻撃者のものであった場合と,第三者のものであった場合を区別し,後者の場合には,第三者の利益保護の見地から,正当防衛の成立については慎重な判断が必要である(同旨,澤井164頁以下)。】(65頁)
⑦和田真一「民法720条」大塚直編『新注釈民法(16)債権(9)712~724の2』(有斐閣,2022年9月)
【民法720条との違いは,刑法の正当防衛は,侵害者に対する反撃だけであり,第三者に対する侵害となったときは,緊急避難として扱われる。刑法では,人の行為によると物によるとにかかわらず,危険から自己または第三者の利益を守るために他人の利益を侵害したときが緊急避難となるが,民法の緊急避難は物による危難に限定され,しかも他人への侵害の場合に緊急避難の成立を認めない。緊急避難について,刑法では広く他の人,他人の物への危険の転嫁を免責するのに民法ではそうでないため,危険を転嫁された人に対する刑事責任は免れても,民事責任は残り得るのである。
このように,民法より刑法の方が違法性阻却事由の認められる範囲が広い。
同じ正当防衛,緊急避難という概念を使用しているとしても,法律の目的は異なる。つまり,民法は権利や法律上保護されるべき利益の保護を目的としているのであるから,自らの権利や利益を守るために,他人の権利や利益を犠牲にすることに厳しい制限を引いている(藤岡144頁)。民法においては,不法行為に対する防衛行為が不法行為者に向けられているか,第三者に向けられているかを問わず責任が阻却され,対物緊急避難でも責任が阻却されるのは,最初の不法行為者に賠償責任を追及できるからである(窪田279頁)。
そうであるにしても,不法行為者に対する反撃型の防衛は正当化されるが,第三者への転嫁型の防衛には一層慎重であるべきであるとして,720条に対する立法論的見直しの主張もある(幾代=徳本103頁)。
その一方で,賠償責任を認めない範囲を広げる方向の議論が,正当防衛,緊急避難以外にも社会的正当行為等を認めることによって行われてきている。
例えば,洪水による被害を防ぐために堤防を破壊した行為について,刑事責任については緊急避難の成立を認め,附帯私訴では緊急避難を認めない判例(大判大3.10.2刑録20輯1764頁)に対して,不法行為者に「期待可能性」がないとして責任免除すべきとされるのは(澤井164頁),このような免責要件拡大の一局面である。】(344~345頁)