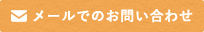労災による休職について、休業補償給付と併せて全額の賃金請求をする手法(労働事件)
2019年10月04日労働事件(企業法務)
近時、労災事件で会社に対して損害賠償請求ではなく、民法536条2項に基づく賃金請求がなされることが出てきました。労働側としては、過失相殺がないというメリットがあるようです。
以前は就労の意思と能力がないということで否定されていましたが、近時認める裁判例も出てきています。民法536条2項の請求が認められるとなると、労働者は、労災保険の休業補償給付と併せて満額の賃金請求ができるということになります。その上で、もらった休業補償給付を労災保険に返還すると。
迂遠な手続になりますし、使用者側としては満額払わなければならなくなるわけですから、労災保険に保険料を払う意味がわからなくなります(支払い義務が出たときのためにみんなで保険料を出しているのに、全額払わされることになるからです)。
近時認めた裁判例として、長崎地方裁判所平成30年12月07日(労働判例1195号5頁)があります。
岩出誠編集代表『労災民事賠償マニュアル 申請、認定から訴訟まで』(ぎょうせい、2018年8月)4頁
【注目すべきは、最近、有力学説において、労災民事(賠償)事件の賃金全額の請求原因として、民法536条2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」の帰責事由(債権者の責めに帰すべき事由)が、①の損害賠償請求の場合の過失。帰責事由と変わらないとして、同項に基づく請求を認める見解が示され(谷口知平ほか編・甲斐道太郎著『新版・注釈民法(13) 〔補訂版〕』684頁[有斐閣、平成18年]、明確には土田。労契法247頁、同旨、荒木。労働法123頁。これに対して、従前の学説は、同項が適用されるのは、労働者が債務の本旨に従った通常の労務の提供の意思と能力の存在を前提としているとして、その適用は認めていなかった。例えば、北岡大介「メンタルヘルス休職者に対する休職期間満了を理由とした解雇と労基法19条」労旬1705号45頁以下参照)、裁判例でもこれをも認める高裁裁判例が現れ(東芝深谷工場事件。東京高判平成23年2月23日労判1022号5頁。地裁レベルでは、同事件(原審) ・東京地判平成20年4月22日労判965号5頁、新聞輸送事件・東京地判昭和57年12月24日労判403号68頁、アイフル(旧ライフ)事件・大阪高判平成24年12月13日労判1072号55頁。同項の適用を否定するのがアジア航測事件・大阪地判平成13年11月9日労判821号45頁、学校法人専修大学事件・東京高判平成25年7月10日労判1076号93頁等)、今後の推移が注目される。なぜなら、これを認めた場合、賃金部分については労基法76条や労災法14条の適用の余地がなくなり(水町勇一郎「労使が読み解く労働判例④」季労229号129頁もこれを指摘する。この点で、労災保険制度趣旨・沿革にも造詣の深い西村健一郎「判例評釈」ジュリ1398号261頁が同項の適用を無批判に支持するのには意外な感がある)、労災補償制度を設けた趣旨や、使用者の保険利益を喪失させる解釈として重大な疑問がある。もし、かかる解釈が定着するような事態を迎えた場合には、労基法、労災法につき、賃金支払の場合の使用者の国に対する労災保険給付相当額の求償を認めるような調整につき、立法的対応が必要であろう(なぜなら、同様な問題といえる、企業が損害賠償義務を履行した場合に、将来給付分が控除されないとしたら、その将来給付分は、本来、企業が賠償しなければ国から被災者や遺族に対して支払われたはずのものであるとして、企業が、被災者側に支払った将来給付分の損害賠償金について、本来保険給付がなされるべきものを国に代わって立替払したとして代位請求したところ、三共自動車事件・最一小判平成元年4月27日民集43巻4号278頁は国に対して未支給の労災保険金を使用者に支払えと代位請求してもこれを認めていない。そこで、立法的な解決が求められるのである)。】