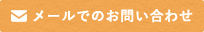交通犯罪弁護要領(救護義務・報告義務違反の例)
(以下の記述は、2024年10月10日現在のものになります)
私は、危険運転致死事件を含む、多数の交通事故事件、道路交通法違反事件の刑事弁護に取り組んできました。
私は、交通事件については、弁護士が捜査段階から刑事弁護人として関与することで、依頼者により有利な結果が出ることが多いということを確信しています。残念ながら、弁護人がついていない場合は、警察官からの誘導により、客観的事実と反する自白調書が作成されてしまったり、証拠の検討が不十分なまま起訴されてしまうことがあるからです。
もっとも、弁護士をつけた場合にどういうメリットがあるのかはわかりにくいと思います。そこで、私が、救護義務・報告義務違反(ひき逃げ・当て逃げ)事件の刑事弁護を受任した場合の一般的な弁護要領について説明いたします。但し、事案により対応は異なりますので、これは一例ということでご理解ください。
犯罪の成否の判断
まず、救護義務・報告義務違反が成立する事案か否かの見極めが必要です。
(1)「道路」該当性の判断
第一に、当該事故現場が、道路交通法2条1号の定める「道路」【道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。】にあたるかどうかを検討しなければいけません。「駐車場」や「コインパーキング」で問題になります。これは一概にはいえませんし、最終的な検察官の判断と、警察官の判断が異なることもあります。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路及び道路運送法に規定する自動車道以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいうとされています。
この判断にあたっては、「道路の体裁の有無」、「客観性・継続性・反復性の有無」、「公開性の有無」及び「道路性の有無」を検討するのが一般的です(道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(19訂版)』(東京法令出版,2024年1月)5頁~)。
「駐車場」がこれを満たすかですが、事実上通り抜けできるというというだけでは、あたらないといえるのではないかと考えます。私のした事例でも、警察で酒気帯び運転として立件された事案が、意見書を出して嫌疑不十分不起訴になったことがあります。
※「道路」該当性に関する最高裁判例
最二小決昭46年10月27日(裁判集刑181号1012頁)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=59548
【右駐車場は、公道に面する南側において約一九・六米、川に接している北側において約一四・一米、南北約四七米のくさび型の全面舗装された広場であって、そのうち東側および西側部分には、自動車一台ごとの駐車位置を示す区画線がひかれ、南側入口には、県立無料駐車場神奈川県と大書された看板があって、本件の広場の全体が自動車の駐車のための場所と認められるところであるから、駐車位置区画線のない中央部分も、駐車場の一部として、該駐車場を利用する車両のための通路にすぎず、これをもつて道路交通法上の道路と解すべきものではない。ホテルなどの利用客等のうちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによって右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。】としています。
(2)「交通事故」該当性の判断
交通事故とは、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」をいうとされています(道路交通法67条2項)。
※道路交通法
(危険防止の措置)
第六十七条
2前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
ア、「人の死傷」について
軽傷でも、「人の死傷」にはあたると考えられています。ただし、車両等の交通と相当因果関係を持つ必要がありますので、駐車場の駐車区画に停車している車に人が転んでぶつかってきたような場合は、「車両等の交通と相当因果関係」を欠きますので、交通事故にはあたりません(降車時のドア開閉事故はあたる場合があります)。
もっとも、「傷害」があれば、いかなる場合でも救護義務違反が成立するわけではないです。
※救護義務に関する最高裁判例
最高裁昭和45年4月10日(刑集第24巻4号132頁)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50949
【裁判要旨 車両等の運転者が、いわゆる人身事故を発生させたときは、直ちに車両の運転を停止し十分に被害者の受傷の有無程度を確かめ、全く負傷していないことが明らかであるとか、負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した等の場合を除き、少なくとも被害者をして速やかに医師の診療を受けさせる等の措置は講ずべきであり、この措置をとらずに、運転者自身の判断で、負傷は軽微であるから救護の必要はないとしてその場を立ち去るがごときことは許されない。】
さらにいえば、過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)は、もともとの刑法211条2項の自動車運転過失致死傷を移したものですが、同法の「傷害」の意義については、刑法204条の傷害罪の「傷害」と同意義と解釈されています(前田雅英ほか編『条解刑法〔第4版補訂版〕』(弘文堂,2023年3月))868頁)。
そして、この「傷害」については、裁判実務においては、およそすべての生理的機能障害を指すものとは解されていません。(川端博ほか編『裁判例コンメンタール刑法〔第2巻〕[§73~§211]』(立花書房,2006年9月)500頁等)。
この解釈は、道路交通法における「交通事故」の解釈にあたっても、参考にされるべきだと考えています。弁護人としてはこれらの文献を踏まえた指摘をすることになります。
イ、「物の損壊」について
報告義務が生じる物の損壊の程度については、道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(19訂版)』(東京法令出版,2024年1月)779頁は【その物の損壊の程度、具体的危険発生の有無、危険防止措置の要否の如何を問わず、いやしくも物の損壊のあったすべての場合を含むものであって、その程度が軽微であってもよい(昭四三・五二七仙台高裁)】とします。これが一般的な解釈です。なお、伊藤榮樹ほか編『注釈特別刑法第六巻交通法・通信法Ⅰ』(立花書房,1982年11月)347頁は、【物の損壊は、自らの車両の損壊も含む。しかし、交通秩序の回復を目的とする本条の趣旨から、崖にぶつかって自車を走行に差支えない程度に損壊したような自損事故の場合には、交通事故とはいえない。(河上和雄)】としますので、自損事故については成立しないといえる余地があります。
ウ、「人の死傷」、「物の損壊」の証拠について
さらに、被害者が交通事故で「傷害」を負った事実があっても、被害者の「傷害」につき、十分な証拠が存在しない場合もあります(犯罪捜査規範4条1項「捜査を行うに当たっては、証拠によって事案を明らかにしなければならない。」)。
下記文献のとおり、重症であれば診断書がなくても人身事故として取り扱われるのが一般です。
Top OSAKA2022年2月号別冊 論文の目ダマ2022 243頁
【2 本事例における基本方針
(1)設問における事例は、事故により一方の運転者が怪我をしていることが客観的に明らかであることから、人身事故として捜査することを基本とし、示談の申出とは明確に区別する。
(2)診断書については、当事者から得られないのであれば、診察した医師に対する照会又は取調べ等、捜査活動により、怪我の程度を明らかにするよう努める。】
そのため、「傷害」の証拠が問題になるのは、自訴のみで診断書が発行されるむちうち症や、後日に診断書が発行された場合などです。弁護人としては、「傷害」の事実が証拠によって認定されるものかを十分吟味し、適切な指摘しなければなりません。具体的には、診断書の内容(むち打ちなど客観的所見なし)、車の損傷状況(修理不要)、診断書の作成時期(事故から数日以上経過して作成)、以後の治療経過(通院なし)などから傷害の事実が証拠に基づいて認定できない、といった意見を述べます。傷害の認定につき、岸洋介「正当防衛に関する近時の判例の動向及び捜査実務上の留意点」捜査研究2015年7月号(773号)2頁~は診断書を鵜呑みにしてはいけないということが記載されていますので、私はこの論文を添付することも多いです。
弁護人の活動次第では、後日に診断書が提出されたとしても、最終的に人身事故として処罰や行政処分がなされないこともあります。私自身の解決事例を紹介いたします。
【解決事例】
一方、「物の損壊」については、人の死傷より明確であることが多いですが、事故直後の写真がない場合や、接触箇所と修理場所が異なるといった場合には、警察官に対して慎重な吟味を依頼しなければなりません。
これらの「人の死傷」や「物の損壊」についての証拠については、民事交通事故訴訟の知見が役に立ちますが、ここでは詳細の記載は省略いたします。
(3)「救護・報告義務違反」該当性の判断
さらに、「交通事故」であるからといって、必ずしも救護・報告義務違反になるわけではありません。
※道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
救護義務違反の「故意」について
救護義務違反は故意犯なので、車両等の運転者に「車両等の交通による人の死傷」(道路交通法72条1項、同67条2項)についての認識が必要です(最三小判昭和45年7月28日刑集24巻7号569頁、最三小決昭和47年3月28日刑集26巻2号218頁)。すなわち、「接触した」という未必的認識のみでは足らず、「負傷したのではないか」という認識が必要です。
そして、文献の記述を詳細に見ると、いずれの文献も「衝突の認識」=「人の負傷の認識」とはしておらず、歩行者の転倒や、ある程度強度の衝突があることが、「人の負傷」の認識を推認するために必要と考えているようです。
結局のところ、【認識の有無についての認定判断は、個々の事案について、具体的状況に基づいて、合理的に行わなければならない。一般的には、後記(2)の裁判例からも明らかなように、事故発生時の現場の状況(見通し、明るさ)、衝突・接触状況(位置関係、衝突・接触部位、衝突音・衝撃の程度、被害者の転倒状況)、車両破損状況、制動状況(制動痕等)、加害者の行動状況(現場確認、現場への引返し)、加害者の飲酒・酩酊の程度・状況、被害者の受傷状況、受傷についての加害者への告知状況等を総合して認定判断している。】(五十嵐義治「不救護・不申告事犯」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書14 交通犯罪(4訂版)』(東京法令出版,2008年4月)の273頁)ということです。
例えば、衝突の認識すらなく、相手もよろけただけの事件などではこの故意を認定することは難しいでしょう。
オ、報告義務違反の「故意」について
報告義務違反も故意犯なので、車両等の運転者に「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」(道路交通法72条1項、同67条2項)についての認識が必要です(最三小判昭和45年7月28日刑集24巻7号569頁、最三小決昭和47年3月28日刑集26巻2号218頁)。すなわち、「接触した」という未必的認識のみでは足らず、「人が死傷した」あるいは、「物が損壊したのではないか」という認識が必要です。ただ、運転者に感じられる程度の衝撃があった場合は、少なくとも「物の損壊」について未必的認識があったとされることが多いでしょう。(佐藤隆文ほか『3訂版 新・交通事故捜査の基礎と要点』(東京法令出版,2022年2月)145頁等)。
カ、「故意」の発生時期について
さらに、「いつ気がついたのか」という点も無視できません。
近時の検察官の文献では、事故により人を死傷させたことの認識も、事故発生から極めて近接した時期に有していなければならないとする指摘があります(横澤伸彦「実例捜査セミナー 死亡ひき逃げ事故事案において,争点を見据えた捜査が功を奏した事例」捜査研究2020年1月号(831号)43-50頁(48頁))。
(3)義務違反の判断
これらの事項を検討した上で、さらに救護・報告義務違反があるかを検討します。ただ、この要件はかなり厳しいので、立件された場合には争うことが難しい場合が多いです。(村上尚文著『刑事裁判実務大系4(ⅱ)道路交通(2)』(青林書院,1993年9月)718頁等)。
古い裁判例では救護・報告義務違反の成立を否定したものもいくつかありますが、それは昔は携帯電話がなく、救急車をすぐに呼べなかったといった事情があったからであり、現在では、よほどの場合でなければ救護・報告義務が発生しているとされながら、それを履行しなかったことが違反とされることはないでしょう。
ただ、重要な例外があります。それは、被害者が激高して襲いかかってきたような場合です。裁判例を引用します。
令和1年7月17日/東京高等裁判所/判決/平成31年(行コ)62号
事件名 運転免許取消処分取消請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却
上訴等 上告受理申立て(後、不受理)
出典
判例地方自治463号90頁
【(2) 法72条1項前段の法令解釈について
控訴人は、法72条1項前段の趣旨目的ないし保護法益に照らせば、原判決が救護義務を負わないとした「交通事故の被害者が加害者に危害を加えようとしていたことが見とれる場合」を最高裁昭和45年判決のいう加害者が救護義務を負う場合の例外と同じように処理することはできない旨主張する。
しかしながら、上記のような場合には、交通事故の被害者は加害者による救護を望むどころか、かえって加害者による救護を自ら困難ならしめているのであるから、最高裁昭和45年判決のいう「負傷が軽微なため被害者が医師の診察を受けることを拒絶した等の場合」に準じるものと解するのが相当であり、救護義務は生じないか又は同義務は解除されるに至ったと解するのが相当である。したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
また、控訴人は、上記主張を前提に、憤慨した被害者が加害者に危害を加えようとしていたことが見て取れる場合でも、加害者は車両内にとどまったまま119番通報をして救急隊を要請する等の方法を採ることは可能であるから、救護義務が消滅すると解するのは相当ではない旨主張する。しかしながら、憤慨した被害者が加害者に危害を加えようとしていたことが見て取れる場合であるにもかかわらず、加害者に車内にとどまったまま119番通報等をすることを求めるのは、加害者に困難を強いるものであり、現実的でもないから、上記主張を直ちに採用することはできない。】
なお、救護義務違反については、道路交通法117条2項違反として擬律されていることが多いですが、運転者に過失がない場合、また降車時のドア開閉事故の場合は、「当該運転者の運転に起因するもの」にあたらず117条1項の適用が問題になります。
存在する証拠の検討
私は、以上の検討を踏まえた上で、当該事件で、いかなる証拠が存在すると考えられるか、その証拠をどうやれば収集できるか、ということを検討します。この時には、警察官向けの捜査要領が記載された文献が役に立ちます。弁護人としては、依頼者に犯罪が成立しないことを示すためにはいかなる証拠が考えられるか、それを弁護人自身が取得できるか、あるいは警察に対して証拠収集を依頼すべきか、等を検討します。
ここはまさしく事案に応じた判断になるのですが…特に重傷事故の場合は、警察は全力で犯人を特定し、逮捕に踏み切ります。一般論として、逃げ切れるとは思わない方がいいです。捜査手法は年年進歩しています。私の場合は、逮捕回避の可能性が高められることと、減刑される可能性が高められることを重視して、自首を勧めています。
(川上拓一編著『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』(学陽書房,2022年2月)58頁参照)。
否認事案でも、出頭して警察に対して十分な捜査を求めるということが考えられます。
ただ、否認事件については難しい問題があり、逮捕されたとしても、完全黙秘を続ければ、ひき逃げ事案として起訴されない可能性はあります。私はやったことがないですが、そういう方針をとる弁護士もいると思います(どちらの方針が良いと一概に判断はできません)。
逮捕の可能性の検討
これも、1と2の結果を踏まえた個別判断になっていくので、一概にはいえません。ただし、現場から逃走しているという事実がある以上、一般論として逮捕の可能性は高いと思った方がいいです。下記ページをご参照下さい。
その他
(1)被害者との示談交渉について
被害者との示談交渉については、任意保険会社に委ねています。
私自身が交渉した事案はないです。
(2)行政処分について
行政処分については、刑事処分とは別個で進みます。行政処分を回避するためには、意見書を警察署と検察官の双方に提出することが大事です。刑事処分が嫌疑不十分不起訴となった場合でも、公安委員会から「救護義務違反」として免許取消処分がなされる可能性があるからです。
私は、処分を回避するためには、警察に対しても「ひき逃げ」にあたらないことの意見書を出して、ひき逃げとしての「違反等登録」の対象にならないようにしておくことが大事だと考えています。あまり意識されていないのですが、手続の流れとして、警察署等が認知した交通違反等については、その登録等に必要な関係書類を都道府県警察本部の行政処分担当課が審査のうえ違反等登録を行います。公安委員会の告知・聴聞はその後の手続です(道路交通研究会「交通警察の基礎知識196 行政処分の迅速かつ確実な執行について」月刊交通2019年2月号(611号)82頁)。
従って、警察段階で「違反等登録」を回避できれば、免許取消処分の手続まで進まないのです。違反等登録票の作成は通常迅速になされていますが、ひき逃げ事件等の特殊な案件は除かれています(那須修『実務Q&A 交通警察250問』(東京法令出版,2021年9月)277頁)。
(3)報道回避について
また、社会的地位のある方の場合、報道発表を強く怖れられていることもあります。そういう場合は、逮捕を回避することが重要ですが、あわせて報道発表を回避してもらうように上申することもあります。
警察の事件事故報道の基準については、インターネット上に明確な情報が見当たりません。警察官向けの昇任試験雑誌などには書かれているのですが、実は「個別判断」です。逮捕事件については原則として逮捕直後に発表されますが、在宅事件については、個別事案に応じて、報道発表するか否か、実名報道をするか否かといったことが決められています。実名報道ではなくても、容易に特定できる形で報道発表がされることもあります。捜査に対する被疑者の態度、弁護活動も含めて判断していると考えられますので、弁護人から警察署宛に、意見書や実名報道が不適当な事案であることを示す資料の提出をしてもらうと良いでしょう。
重松弘教(警察庁長官官房総務課広報室長)「「広報」を広報する」(警察公論2016年9月号)4-9頁
6-7頁
【さらにその態様から、①事件広報、②危機管理広報、③積極広報、④事態対処広報の4つに大別することができます。「事件広報」は従来から警察広報の中心で、事件の発生検挙等に関する広報です。公表による公益性(広報の目的)と公表による不利益(関係者の名誉・プライバシーの侵害、捜査への支障等)等を総合的に勘案して、個別事件ごとに広報するか否か、広報する場合はどの範囲で行うべきか等を判断しなければなりません。個別具体的に検討を要することから。全国一律の基準はありません。】
(4)立件回避の弁護活動について
また、実務的には、厳密には犯罪が成立するとしても、軽微な事案では立件されないこともあります。そういった場合は、事件価値から立件を回避すべきといったことも述べます。
刑事訴訟法189条2項は「法警察職員は,犯罪があると思料するときは,犯人及び証拠を捜査するものとする。」と規定していますが、この規定はいかなる犯罪であっても捜査をすべきというものとは解されておらず、いかなる軽微な犯罪であってもすべて捜査しなければならないという絶対的な義務を課するのではなく, 司法警察職員にある程度の合理的な裁量の余地を残す趣旨と解されています(河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法第二版第4巻〔第189条~第246条〕』(青林書院,2012年4月)46頁(馬場義宣=河村博))。
事件価値の判断にあたっては、「国民の捜査に対する期待、要望」を念頭におき、犯罪の主体・客体、軽重・形態・悪性の度合あるいは事件の社会的背景及び影響、捜査の要急性等もろもろの状況考慮するものと考えられていますし、あまりにも微細な事件まで捜査し、検挙することの社会的影響を考える必要があるとされています(警察大学校特別捜査幹部研修所編著『新版 捜査学-捜査指揮総論-』(立花書房,1994年12月)3~4頁)。
まとめ
以上が、私が、救護義務・報告義務違反(ひき逃げ・当て逃げ)事件の刑事弁護を受任した場合の一般的な弁護要領です。もっとも、これは完成したものではありません。私は、継続的に勉強を続けながら、依頼者にとっての最適解を検討しています。ご相談を、お待ちしております。
【参考文献】
(道路交通法解説書)
最高裁判所事務総局刑事局『交通反則通告制度について』(法曹会,1969年2月)
警察庁交通局編『交通警察質疑応答集 5版』(東京法令出版,1975年8月)
警視庁交通部交通総務課『交通関係質疑回答集』(警視庁交通部交通総務課,1975年11月)
法曹会編『例題解説道路交通法〔改訂版〕』(法曹会,1976年5月)
久保哲男『最新実務道路交通法』(立花書房,1979年6月)
木宮高彦・岩井重一『詳解道路交通法〔改訂版〕』(有斐閣,1980年5月)
伊藤榮樹ほか編『注釈特別刑法第六巻交通法・通信法Ⅰ』(立花書房,1982年11月)
園部敏・植村栄治『交通法・通信法〔新版〕(法律学全集15-Ⅰ)』(有斐閣,1984年2月)
警視庁交通部交通総務課法令指導係『交通関係質疑回答集(12)』(警視庁,1986年3月)
警察庁交通局監修『改正道路交通法-昭和61年5月改正-』(大成出版社,1986年6月)
警視庁交通部交通総務課法令指導係『交通関係質疑回答集改訂 総合版(上)』(警視庁,1987年3月)
警視庁交通部交通総務課法令指導係『交通関係質疑回答集改訂 総合版(下)』(警視庁,1988年3月)
東京地方検察庁交通部研究会編『三訂版 道路交通法辞典 上巻』(東京法令出版,1988年5月)
東京地方検察庁交通部研究会編『三訂版 道路交通法辞典 下巻』(東京法令出版,1988年5月)
荒木友雄編『刑事裁判実務大系5 交通事故』(青林書院,1990年1月)
交通法令実務研究会編『改訂 逐条道路交通法』(警察時報社,1991年2月)
平野龍一編集代表『交通編(1) [第二版] (注解特別刑法第1巻道路交通法)』(青林書院,1992年6月)
村上尚文著『刑事裁判実務大系4(ⅰ)道路交通(1)』(青林書院,1993年9月)
村上尚文著『刑事裁判実務大系4(ⅱ)道路交通(2)』(青林書院,1993年9月)
警察庁交通局監修『平成9年改正道路交通法の解説』(大成出版社,1997年10月)
交通法令実務研究会編『改訂 逐条/道路交通法 改訂増補』(警察時報社,2004年5月)
橋口榮四郎『平成17年版 わかりやすい道路交通法辞典』(東京法令出版,2005年7月)
橋本裕蔵『道路交通法の解説十二訂版』(一橋出版,2007年12月)
小川賢一『新実務道路交通法』(立花書房,2008年11月)
交通実務研究会編著『早わかり道路交通法〔改訂版〕』(立花書房,2011年7月)
交通制度研究会編著『交通警察101問(改訂第2版)』(立花書房,2011年8月)
法務総合研究所『研修教材五訂道路交通法』(法務総合研究所,2013年3月)
牧野隆編著『図解 交通資料集 第4版』(立花書房,2015年12月)
道路交通研究会編『わかりやすい道路交通法の改正要点(法律平成27年6月公布)』(東京法令出版,2016年9月)
道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(17訂版)』(東京法令出版,2017年5月)
運転免許研究会『点数制度の実務[8訂版]』(啓正社,2017年7月)
道路交通法令研究会編著『注解道路交通法〔第4版〕』(立花書房,2018年3月)
道路交通法令研究会編著『注解道路交通法〔第5版〕』(立花書房,2020年2月)
警察協会編『地域警察活動(交通)』(警察協会,2020年3月)
牧野隆編著『図解 交通資料集 第5版』(立花書房,2020年11月)
運転免許研究会『点数制度の実務[9訂版]』(啓正社,2020年12月)
道路交通法実務研究会編『アイキャッチ 図解 道路交通法 6訂版』(東京法令出版,2020年11月)
道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18訂版)』(東京法令出版,2020年11月)
道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18-2訂版)』(東京法令出版,2022年11月)
矢代隆義『概説 交通警察〈第2版〉-交通警察活動の歴史と構造-』(立花書房,2022年12月)
道路交通研究会編『交通局発足60周年記念 交通警察の歩み』(東京法令出版,2023年2月)
道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(19訂版)』(東京法令出版,2024年1月)
(救護・報告義務関係論文)
本江威憲「道路交通法」西原春夫ほか編『判例刑法研究 第8巻 特別刑法の罪』(有斐閣,1981年3月)419-448頁
川上拓一「16 ひき逃げの刑事責任」荒木友雄編『刑事裁判実務大系5 交通事故』(青林書院,1990年1月)
東京地方検察庁交通部実務研究会「交通事件における捜査上の諸問題(その11)~報告義務違反について~」月刊交通2003年4月号(407号)63-38頁
東京地方検察庁交通部実務研究会「交通事件における捜査上の諸問題~報告義務違反について」捜査研究2003年6月号65-67頁
杉本一敏「負傷者救護義務違反罪の罪質と客観的成立要件」曽根威彦ほか編『交通刑事法の現代的展開 岡野光雄先生古稀記念』(成文堂,2007年2月)
梶美紗「実務刑事判例評釈[Case343]東京高判令5.4.12道路交通法72条1項後段の報告義務が消滅し得る例外的な場合に当たらないとして同義務違反を認めた事例(確定)」警察公論2024年4月号86-95頁
(交通行政処分関係論文)
道路交通研究会「交通警察の基礎知識(114)点数制度によらない処分」月刊交通2012年4月号(523号)76-81頁
山口貴史(警察庁交通局運転免許課)「最近の運転免許の行政処分に関する行政事件訴訟の裁判例から」月刊交通2018年2月号(599号)21-30頁
道路交通研究会「交通警察の基礎知識196 行政処分の迅速かつ確実な執行について」月刊交通2019年2月号(611号)82-86頁
道路交通研究会「交通警察の基礎知識254 運転免許の行政処分」月刊交通2023年12月号(675号)77頁
(交通事故・事件判例集)
最高裁判所事務総局刑事局編『自動車による業務上過失致傷事件に関する刑事裁判例集』(法曹会,1967年11月)
我妻栄編集代表『交通事故判例百選』(有斐閣,1968年4月)
加藤一郎ほか編『交通事故判例百選(第二版)』(有斐閣,1975年8月)
最高裁判所事務総局編『自動車による業務上過失(重過失)致死傷事件に関する刑事裁判例集』(法曹会,1985年8月)
加藤一郎ほか編『新交通事故判例百選』(有斐閣,1987年9月)
川端伸也『交通事故刑事判例要旨集』(日世社,1988年4月)
法総研誌友会研修編集部『基本判例解説 交通事犯』(法務総合研修所,1990年2月)
村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第1巻発車(その1-前進)の際の事故』(日世社,1992年11月)
村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第3巻佇立・飛出し・横断者等に対する事故(その1)』(日世社,1993年10月)
村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第2巻発車(その2-後退)の際の事故』(日世社,1993年12月)
村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第4巻佇立・飛出し・横断者等に対する事故(その2)』(日世社,1993年12月)
村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第5巻佇立・飛出し・横断者等に対する事故(その3)』(日世社,1994年12月)
村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第6巻追越し、追抜きの際の事故(その1-対自転車)』(日世社,1997年3月)
村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第7巻追越し、追抜きの際の事故(その2-対自転車・人)』(日世社,1998年4月)
村上尚文編『捜査実務重要裁判例集・交通編』(立花書房,1988年8月)
宮原守男ほか編『交通事故判例百選[第四版]』(有斐閣,1999年9月)
交通判例研究会編『【5訂版】交通判例ハンドブック』(近代警察社,2004年10月)
江原伸一著『実務に役立つ最新判例77選 交通警察』(東京法令出版,2013年3月)
江原伸一著『実務セレクト交通警察110判例』(東京法令出版,2017年8月)
交通事件判例研究会編著『必携 自動車事故・危険運転重要判例要旨集〔第3版〕』(立花書房,2022年11月)
交通事件判例研究会編著『必携 交通事件重要判例要旨集〔第3版〕』(立花書房,2024年3月)
(交通事故・交通違反事件捜査実務書)
安西温・三ツ木健益共著『自動車事故による業過犯の捜査』(警察時報社,1990年3月)
交通捜査研究会『-新任交通警察官から幹部まで-徹底解説 交通事故事件捜査』(東京法令出版,1998年2月)
交通警察実務研究会『交通捜査実務パーフェクトガイド』(東京法令出版,2000年1月)
交通捜査研究会編著『交通捜査実務の手引き~捜査要領と犯罪事実記載例~』(東京法令出版,2000年12月)
交通実務研究会編著『新版 交通事件供述調書記載例集』(立花書房,2002年1月)
交通実務研究会編著『新版 交通事件捜査報告書記載例集』(立花書房,2002年1月)
窪田四郎ほか著『交通事故捜査 Ⅰ業務上過失致死編』(近代警察社,2002年11月)
窪田四郎ほか『-3訂版-交通事故捜査Ⅲ-その他の刑法犯編-』(近代警察社,2003年1月)
交通実務研究会編『改訂版 交通実務ハンドブック2』(東京法令出版,2003年3月)
交通鑑識研究会編『交通捜査実務教本-捜査実務編-』(東京法令出版,2003年5月)
交通鑑識研究会編『交通捜査実務教本-捜査書類編-』(東京法令出版,2003年5月)
藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書14 交通犯罪(4訂版)』(東京法令出版,2008年4月)
交通実務研究会編著『実務に直結した新交通違反措置要領〔六訂版〕』(立花書房,2008年10月)
福岡県警察本部交通部交通指導課編著『改訂版 交通事故鑑識』(東京法令出版,2009年7月)
東京地方検察庁交通部実務研究会『改訂版交通事故事件捜査110講』(警察時報社,2009年9月)
交通実務研究会編著『新外国人交通事件捜査-捜査書類記載例付』(立花書房,2009年12月)
交通実務研究会編著『新交通事件捜査報告書記載例集』(立花書房,2009年12月)
渡邊坦『六訂版 交通特殊事件 捜査書類作成の手引きⅠ』(東京法令出版,2010年2月)
交通実務研究会編『新 交通事件捜査書類作成要領〔補訂版〕』(立花書房,2010年7月)
警察実務研究会編著『クローズアップ実務Ⅰ交通違反否認事件の措置要領〔Part1〕〔補訂版〕』(立花書房,2010年8月)
警察実務研究会編著『クローズアップ実務Ⅳ交通違反否認事件の措置要領〔Part2〕』(立花書房,2010年8月)
富松茂大編著『新 自動車事故供述調書記載要領〔実況見分調書現場見取図付〕』(立花書房,2010年11月)
交通実務研究会編『2訂版交通実務ハンドブック1交通反則切符等作成の手引』(東京法令出版,2011年3月)
交通実務研究会編『交通切符・交通反則切符作成の指針 交通実務の手引 17訂版』(警察時報社,2011年5月)
交通実務研究会編著『自動車事故捜査手帖 改訂11版』(警察時報社,2011年9月)
交通実務研究会編『交通切符・交通反則切符作成の指針 交通実務の手引 改訂19版』(警察時報社,2012年7月)
宮田正之編著『すぐに役立つ わかりやすい交通事故事件一件書類記載例集』(立花書房,2012年7月)
宮成正典『交通事故捜査の手法 第2版』(立花書房,2014年2月)
渡邊坦『八訂版 地域・交通警察官のための犯罪事実記載例集』(東京法令出版,2014年7月)
千葉県警察本部交通捜査・鑑識実務研究会編『交通捜査・鑑識実務必携』(立花書房,2014年7月)
交通実務研究会編著『過失運転致死傷・道路交通法違反 強制捜査関係書類作成の手引き 第4版』(立花書房,2014年12月)
警察実務研究会編著『クローズアップ実務交通違反否認事件の措置要領セレクト16事例』(立花書房,2015年2月)
富松茂大『自動車事故の過失認定』(立花書房,2015年3月)
交通実務研究会編『2訂版交通実務ハンドブック2 交通事故事件書類作成の手引』(東京法令出版,2015年4月)
兵庫県警察本部交通部交通捜査課編『五訂版 交通事故事件捜査実務必携』(東京法令出版,2015年4月)
交通事故・事件捜査実務研究会編著『自動車事故犯罪事実作成実務必携』(立花書房,2015年8月)
交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事故・事件令状請求の手引き 第4版』(立花書房,2015年8月)
★那須修編著『当直責任者も必読!警察署における交通捜査ハンドブック』(立花書房,2015年10月)
恩田剛編著『令状審査の視点から見たブロック式交通事件令状請求マニュアル』(立花書房,2015年12月)
富松茂大『自動車事故の供述調書作成の実務-取調べの基本と応用-』(立花書房,2016年11月)
那須修『実務Q&A 交通警察222問』(東京法令出版,2017年1月)
交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故・事件捜査実務必携~過失認定と実況見分,交通捜査の王道~』(立花書房,2017年7月)
交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事件犯罪事実作成実務必携』(立花書房,2017年8月)
城祐一郎『Q&A 実例交通事件捜査における現場の疑問〔第2版〕』(立花書房,2017年10月)
交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事件犯罪事実記載例集』(立花書房,2018年8月)
交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事故犯罪事実記載例集』(立花書房,2018年8月)
交通事故・事件捜査実務研究会編『すぐに役立つ・わかりやすい交通事件犯罪事実・情状意見記載例集〔第2版〕』(立花書房,2018年12月)
交通事故・事件捜査実務研究会・那須修編著『交通事故・事件一件書類作成実務必携〔第2版〕』(立花書房,2020年6月)
木村昇一編著『交通事故・事件,交通違反供述調書記載例集〈第6版〉』(立花書房,2021年7月)
交通捜査実務研究会編『八訂版 交通捜査提要』(東京法令出版,2019年9月※2021年6月補正)
那須修『実務Q&A 交通警察250問』(東京法令出版,2021年9月)
那須修編共著『プロ直伝!交通捜査のQ&A』(東京法令出版,2021年9月)
交通事故・事件捜査実務研究会編著『自動車事故犯罪事実作成実務必携〔第2版〕』(立花書房,2021年9月)
佐藤隆文ほか『3訂版 新・交通事故捜査の基礎と要点』(東京法令出版,2022年2月)
交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故実況見分調書作成実務必携~交通事故実況見分のポイント~』(立花書房,2023年4月)
互敦史『二訂版(補訂) 基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』(東京法令出版,2023年4月)
交通事故・事件捜査実務研究会編『自動車事故犯罪事実作成実務必携【第3版】』(立花書房,2024年4月)
城祐一郎『悪質交通事犯と闘うために~多くの人の涙を背負って~』(東京法令出版,2024年7月)
(交通事故・交通違反事件弁護実務書)
野村龍一郎『ドライバー行政処分対抗法』(オリジン出版センター,1992年6月)
交通法科学研究会編『交通事故事件の弁護技術』(現代人文社,2008年1月)
高山俊吉『交通事故事件弁護学入門』(日本評論社,2008年2月)
今井亮一『最新版なんでこれが交通違反なの!?』(草思社,2010年7月)
高山俊吉ほか『挑戦する交通事件弁護』(現代人文社,2016年4月)
髙山俊吉『入門交通行政処分への対処法』(現代人文社,2017年10月)
高山俊吉『交通事故事件弁護学入門〔第2版〕』(日本評論社,2019年7月)