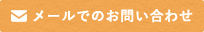須藤典明/清水響・編『労働事件事実認定重要判決50選』
2018年07月20日労働事件(企業法務)
東京地裁労働3か部の著作シリーズです。
以下は、弁護士向けの詳細なレビューです。
近時の労働裁判例のうち、下級審と上級審とで判断が分かれた事案の裁判例を中心に収録しています。裁判例の事実認定の差を説明している部分より、「今後の指針」という欄で、事案の種類に応じて、どういう部分に着目して判断すべきかということまで踏み込んで論じられている部分が重要です。これも労働事件を専門的に取り組む弁護士であればおさえておく必要があるでしょう。
気になった記述をいくつか
「菅野202頁は・・・労働条件の不利益な変更も労働者の合意があれば可能であり、就業規則それ自体やその変更の合理性は必要されないとしているものの、そこでいう「合意の成立」の事実認定において、労働契約法10条の考慮要素が影響する可能性が高い」(72頁)。
←私としては、このような考え方からすれば、同意書があったとしても、就業規則変更による労働条件の引き下げが認められる場合でなければ有効性が認められない方向になるのではないかと思います。
「(タイムカードからの労働時間の推定について)事案ごとに、タイムカードの利用目的(労働時間管理目的か否か)、その利用の実態、労働時間管理の実態、時間帯、業務、特に残業の必要、実態、使用者の態度、事業場にとどまる別理由の可能性等の諸事情を具体的に検討すべきである」(132頁)。
←タイムカードの証明力は高いですが、始業時刻前の前残業はあまり認められません。
「(ビル管理者の仮眠時間等の労働時間該当性について)当事者としては、・・・判断のポイントとなる「労働からの解放の有無」や、その具体的内容ともいうべき「労働契約上の役務提供の義務づけの有無」を基礎づける具体的な事実を適切に取捨選択した上で、充実した主張立証活動を行う必要があると思われる」(145頁)。
←業務マニュアルにまで踏み込んで判断されますので、マニュアルの検討が必要です。
「管理監督者性が認められた裁判例は少ないのが実情であるが、肯定例の内容をつぶさにみると、いずれもさほど特異な例とは思われないし、行政通達で具体化された内容をみても、同様の印象を抱く。使用者側としては、どうせ管理監督者性は認められないから、などと過度に委縮する必要はないものと思われるし、・・・和解による適切な解決を目指す上でも意味のあることと思われる。使用者側としては、その意味で、職務権限、責任、労働時間に関する最良、待遇という面のみならず、企業内での当該管理職の序列なども十分立証して、裁判所の説得を試みるべきであろう。」(158頁)。
←裁判官が使用者側に異例の注文を付けています。
注釈でも、管理監督者性が認められる余地があるケースでも、使用者が反対の結論が出るリスクを考慮して和解による解決を志向している場合が多いのではないかと推測され、それが肯定例の少ない原因の一つではないかとも推測される、としています。
実務的には中小企業での管理監督者は取締役に近いクラスでないと認められ難いという印象があり、使用者側が最初から諦めるパターンが多いです。実際どの文献でも管理監督者性には厳しい判断が下される、とされています。その実務運用に一石を投じる内容と思いました。
「一見すると懲戒事由に該当する事実が些細なもののように見えても、当該会社の業務内容や性質によっては重大なものと評価せざるを得ない場合もある。逆に懲戒処分をするにしても、懲戒解雇を選択する場合は、その相当性は身長に判断されることになる。最終的にはその時々の社会情勢、社会常識に従って判断せざるを得ないところである。」(296頁)。
←例えば、遅刻については一般的には比較的軽微な非違行為とされますが(269頁)、例えばプレゼンの場面など、絶対に出席が必要な場面で寝坊して遅刻したといったことであれば、それなりに重大な非違行為といえます。具体的にどれだけ企業秩序を乱す行為であったかということの主張立証が重要です。
「(山梨信金事件について)その内容は合意解約も労働契約を解消する不利益変更の一場面であることから参考になる点がある」(326頁)
←類型別労働関係訴訟の実務347頁では、退職の意思表示は類型的に労働者にとって不利益な意思表示であるといえない、としており、ニュアンスに差異がある。確定的な意思表示であること以上に山梨信金事件のような「労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か」ということまで求めるのは疑問です。
特に気になった事件として、33事件(東京高裁平成27年4月16日判決、労働判例1122号40頁)があります。懲戒を受けたことのない勤続19年の従業員に対する能力不足での解雇を有効とした事例ですが、控訴審の判決では「Y(使用者)が15名ほどの職員しか有しない小規模事業所であり、その中で公法人として期待された役割を果たす必要があったこと」が、解雇を有効と判断するにあたり、重視されたと考えられる事実とされています。
そして、この裁判例については、「本判決は、これまでの裁判例で示されてきた考え方に沿って、労働者の職務遂行能力の不足を理由とする解雇の有効性について、原審と異なる判断を示した事例である。本判決の枠組み自体は、特段目新しい考え方を提示したものではなく、上告受理申立ても否定され、控訴審の判断が維持されている・・・」ものと評価されています。
つまり、小規模事業については、小規模事業ということを踏まえた上で、小規模事業の従業員としての必要な資質・能力が問うべきだ、ということです。この、会社規模によって必要とされる能力の程度や使用者の解雇回避努力義務の程度が異なるということは使用者側弁護士や一部の裁判例で述べられてきたことです。当然のことなのですが、このことが明示されたことは良いと思います。
http://tachibanashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=3404