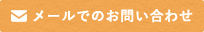社長が従業員と不倫をすることは、不同意性交等罪になるかという相談(性犯罪、刑事弁護)
2024年09月11日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は会社経営者です。秘書として雇った従業員と不倫していたのですが、勤務態度が悪いので解雇して不倫関係を解消しようとしたところ、不同意性交等罪で警察に行くといわれました。彼女は不倫をしていることをわかっているのですから、私の妻から慰謝料請求を受ける立場だと思うのですが、そんなことは認められるのでしょうか。
A、警察が不同意性交等罪として立件することは十分考えられます。特に、どういう経緯で性的関係を持ったかが重要になります。
【解説】
令和5年に性犯罪を立件しやすくするために刑法が改正されました。かつては、セクシャル・ハラスメントとして扱われていた事案についても、性犯罪として取締りがなされる傾向になっています。社長と従業員といった関係における性的交渉については、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」したものだとされるリスクが上昇しています。その後に交際関係が続いていたとしても、「迎合行動である」として、当初の性交渉が不同意性交等とされる危険性があります。仮に不同意性交等罪となれば、不貞相手としての慰謝料支払義務も否定されるでしょう。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を認めた最判昭和54年3月30日民集第33巻2号303頁も「故意又は過失がある限り」とあり、第三者が損害賠償責任を負うのは、あくまで自由意志で既婚者と肉体関係を持ったことを前提にしていると考えられます。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53272
- 判示事項
- 妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持ち同棲するに至つた女性の行為と右未成年の子に対する不法行為の成否
- 裁判要旨
- 妻及び未成年の子のある男性が他の女性と肉体関係を持ち、妻子のもとを去つて右女性と同棲するに至つた結果、右未成年の子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、右女性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。
【しかし、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。】
【参考文献】
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
社長と従業員の不倫関係は「不同意性交等罪」に該当し得るか:法的・実務的検証
概要: 社長(経営者)と従業員との間で不倫関係が継続していた場合、当初の性的関係が本人の意思に反して行われたもの(不同意性交等罪)として成立し得るか、またその場合に不貞慰謝料請求(民事上の損害賠償)が認められるかを検討します。刑法解釈の最新動向と捜査実務の視点から、さらに不貞相手の民事責任に関する解釈を踏まえ、問題の妥当性を詳述します。
刑法改正と不同意性交等罪の要件
2023年の刑法改正により、旧来の強制性交等罪・準強制性交等罪が統合され、「不同意性交等罪」(刑法177条)として再定義されました。改正のポイントは、従来必要とされた「暴行・脅迫」や被害者の「抗拒不能」(心神喪失等)の要件を見直し、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」で行われた性的行為を広く処罰対象にしたことです。この「困難な状態」に当たる事由として、改正法176条1項各号は8つの類型を具体的に列挙しており、その中には職場における地位の差による心理的圧力が含まれます。例えば**「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力」により不利益を被ることへの懸念**がある場合が該当し、典型例として「従業員である被害者が、仕事上の権限を持つ社長から性的行為を要求され、応じなければ職を失ったり望まない仕事を押し付けられるおそれがある状況」などが挙げられています。つまり、上司(社長)と部下(従業員)という関係性それ自体が、被害者にとって自由な意思決定を困難にしうる要因として明示されたのです。
そのため、社長と従業員の性的関係は、一見合意に基づく不倫関係に見えても、背後に職務上の地位関係による圧力が存在する場合には「不同意性交等罪」に該当し得ると解されています。改正法の趣旨は、従来であればセクシュアルハラスメントや社内問題として処理されていた事案も、その実質を見て性的同意が欠けていれば刑事事件として立件しやすくすることにあります。実際、社長と部下という力関係下で行われた性的行為は、「被害者が同意しない意思を十分に形成・表明できないまま行われたもの」と評価されるリスクが高まっています。この評価は刑法学的にも妥当であり、改正法の文言に照らしても、形式的な同意があっても被害者の真意に基づかない場合には処罰の対象となり得ると解釈できます。
継続する不倫関係と「迎合行動」の評価
本件で特に問題となるのは、当初の性的関係の後も不倫関係が継続していた場合に、それが初回の同意を基礎付けるのか、それとも被害者の「迎合行動」にすぎないのかという点です。記事では、たとえその後も男女交際が続いていたとしても、それは支配関係下での「迎合行動」に過ぎず、当初の性交渉について不同意性交等罪が成立する可能性があると指摘されています。法律的にも、この見解は近時の裁判例や学説に裏付けられています。例えば、東京高等裁判所平成16年8月30日判決では、大学講師と女子学生の関係で、女子学生が明示的な抵抗をしなかったにもかかわらず性的関係がハラスメント(違法行為)と認定されました。このケースは刑事事件ではなく民事上のセクハラ事案ですが、被害者が抵抗しなかったりその後も表面的に関係を続けた場合でも、それが心理的圧力下での服従にすぎないと評価されれば、真の同意がなかったものと扱われることを示しています。「心理的監禁状態」「強いられた同意」といった概念も議論されており、権力関係の下で生じた性的関係では被害者の沈黙や継続的な関与をもって同意があったとは直ちに言えないとの理解が広まりつつあります。
以上より、不倫関係が継続していた事実だけで当初の不同意性交等罪成立が否定されるわけではありません。むしろ刑法の観点では、初回の性的行為時にさかのぼって真に自由な意思に基づく同意があったかを吟味すべきであり、後日の関係継続はその同意の有無を判断する決定的事情ではないといえます。記事の指摘するように、支配的な職場関係における性交渉は、その後の交際自体が加害者への迎合(服従)として説明されることがあり、初回の行為の違法性を覆すものではない。この点で記事の主張は刑法理論上も妥当と言えるでしょう。
捜査実務における対応と立証
捜査実務の観点からも、近年この種の事案に対する取扱いは厳格化しています。従来なら「社内不倫」とされ見過ごされた状況でも、警察・検察はその実質に着目し、権力関係を背景とする性的強要として扱う傾向があります。実際に、社長と部下のケースで部下が性的被害を申告すれば、警察は単なる雇用トラブルではなく性犯罪の可能性として捜査します。その際、以下のような点が総合的に検討されます:
- 性的行為に至った経緯・状況: 最初の性的関係がどのように始まったか(例えば業務指示の延長で拒み難い雰囲気だったのか、酒席で酩酊状態だったのか等)。
- 時間・場所・周囲の状況: 社内(勤務時間中や社長室等)で行われたか、公私の別や不意打ち性の有無。社内でいきなり性的関係に及ぶのは通常考えにくく、不自然な状況であれば強要を裏付ける事情と捉えられます。
- 当事者の関係性: 年齢差・地位差・力関係の大小、過去の言動(セクハラ的言動の有無)など背景事情。特に上司-部下の関係では、部下が望まない性的関係を拒めなかった可能性を重視します。
- 継続的関係の性質: その後の不倫関係の実態も調べます。メールやLINE等の通信記録から、被害者が嫌々従っていたのか、自発的に関係を続けていたのかを推測します。被疑者(社長)の主張する「合意の関係」が信用できるかも、客観証拠と矛盾がないか慎重に検討されます。
こうした捜査の結果、不同意性交等罪の嫌疑が十分と判断されれば逮捕状が発付されることになります。逮捕状が出るということは「それなりに嫌疑がある」というのが一般論であり、単なる逆恨みによる虚偽申告だけでは通常そこまで至りません。実際、類似の架空相談事例では「部下が誘ってきた一度きりの不倫だ」と弁解する夫に逮捕状が出たケースが紹介されていますが、そのような自己弁護的な主張だけでは捜査機関は動かず、相応の裏付けや状況証拠が揃っていると考えられます。捜査官は「果たして部下が心から望んで社長と社内で性的関係を持つものだろうか?」という常識的な視点も持ちながら、偏らず冷静に真相解明を進めます。結果次第では、被疑者が早期に事実を認め被害者との示談を図る方針を助言されることもあるでしょう。
要するに、実務上も「継続して不倫関係にあった=合意があった」という短絡的判断はされず, 総合的証拠から初回の同意の有無が判断されます。記事の示す「不同意性交となれば刑事立件され得る」という結論は、昨今の捜査実務の動向に照らして適切であり、そのリスク評価は妥当だと言えます。
不貞相手の民事責任(慰謝料)に関する解釈
民法上の不貞慰謝料請求についても、記事は重要な論点を提起しています。一般に、配偶者の不貞行為(不倫)によって精神的苦痛を被った配偶者(妻または夫)は、相手方の不貞相手に対して損害賠償(慰謝料)を請求できます。判例上、その根拠は配偶者の権利(貞操権・平穏な家庭生活を営む権利)の侵害にあり、第三者である不貞相手も「故意又は過失」があれば不法行為責任を負うとされています。有名な最判昭和54年3月30日判決でも、不倫相手(第三者)は誘惑の有無や恋愛感情の自然さに関わらず、故意または過失にもとづき配偶者と肉体関係を持った以上、他方配偶者の権利を侵害する違法行為を行ったものとして慰謝料支払義務を負うと判示されています。
しかしここで重要なのは、「故意または過失がある限り」という要件です。これは換言すれば、不貞相手側に自発的・積極的に既婚者と関係を持つ意思(故意)または注意義務違反(過失)がある場合に限り責任を負うということです。したがって、不貞相手が自由な意思に基づかず関係を持たされた場合(例:強制・欺罔による性的関係)には、この「故意・過失」が欠如しており、原則として不法行為は成立しません。記事のケースで言えば、従業員の女性が不同意性交等罪の被害者であると認定されれば、彼女は社長との性的関係について自らの自由意志で臨んだわけではないため、配偶者(社長の妻)に対する不貞の加害者とはみなされません。刑事上「被害者」である者に民事上「加害者」としての賠償責任を問うことは法理論上矛盾するからです。
実際、記事でも「仮に不同意性交等罪となれば、不貞相手としての慰謝料支払義務も否定されるでしょう」と指摘されています。これは上述の判例理論と整合的です。配偶者から見れば、自身の配偶者が他者に強制的に性的関係を強いられた場合、それは不貞(双方合意の不倫)とは言えず、むしろ犯罪被害です。被害者である第三者に慰謝料請求を認めることは、法律上の因果関係や公平の観念に反します。したがって、不同意性交等罪が成立するような事情では、配偶者は第三者に対する慰謝料請求はできません。この点、記事の見解は民法解釈上も適切であり、誤りはないといえます。
もっとも留意すべきは、実際に刑事事件として立件されなくとも、事実関係として第三者が脅されて関係を持たされた疑いが強い場合には、民事上も不貞慰謝料請求は認められにくいということです。裁判所は不貞慰謝料訴訟において、当該関係が自由意思にもとづくものだったか慎重に判断します。被告(不貞相手)が「自分は抵抗できない状況で関係を強いられた被害者だ」と主張し、それが客観的に裏付けられれば、原告配偶者の請求は棄却されるでしょう。要するに、同じ出来事を不倫と見るか性暴力と見るかで法律関係が一変するため、刑事・民事の両面から事実認定が重要になるのです。
まとめ:記事内容の妥当性と結論
以上の検討から、該当ウェブ記事の主張は刑事・民事両面で概ね妥当であると評価できます。刑法改正により、社長と従業員の関係下での性的行為は不同意性交等罪に該当し得ること、その後不倫関係が続いていても初回の同意欠如を補完するものではないことは、法律学上・捜査実務上ともに支持される見解です。捜査当局も権力関係による性犯罪に厳しく対処する方向にあり、形式的な「合意」や関係継続のみで嫌疑を否定することはありません。むしろ客観証拠に基づき、真に合意がなかったと判断されれば毅然と立件されるでしょう。
また、一方で民事の観点では、不同意性交等が成立するような場合に不貞慰謝料請求を認めないという記事の指摘も正当です。自ら望んだ不倫ではなく被害を受けた立場の者に賠償責任を負わせることは法の趣旨に反するためであり、判例上要求される「故意・過失」が欠ける以上当然の結論です。
総合すると、「社長が従業員と不倫していたが、解雇時に従業員から不同意性交等罪で告訴すると脅された」という事案に対する記事の法的評価は、現行法の解釈および運用に即したものと言えます。もっとも、個別事案では証拠の有無や当事者の供述の信用性が結果を左右します。継続的関係の裏に真の同意があったのか、あるいは恐怖や圧力による服従であったのかはケースバイケースで慎重に判断されるでしょう。しかし原則論としては、権力関係下の性的関係は厳格に精査され、不本意な関係であれば刑事責任が追及され得るし、その場合は民事上の不貞責任は問われないという整理で概ね間違いありません。記事が提示した見解はその原則に則ったものであり、法律専門家に向けた解説としてもおおむね適切なものと評価できます。
参考法令・判例等: 刑法176条・177条(2023年改正)、最判昭和54年3月30日(民集33巻2号303頁)、東京高判平成16年8月30日(判時1879号62頁)ほか。上述の解釈・運用はこれらの条文および判例の趣旨に基づいています。